相続の手続きって、「何から始めていいのか分からない…」という方がほとんどですよね。
しかも、相続税や名義変更、トラブル回避など、考えることが多くて混乱しがちです。
本記事では、2025年最新版の相続手続きの流れと必要書類を初心者にもわかりやすく解説します。
相続順位や財産の評価、税金の申告、トラブル予防策まで、今すぐ知りたいポイントを網羅!
**「このページを見れば相続の全体像がつかめる」**を目指して、スマホでもサクッと読めるよう構成しています。
大切な手続きだからこそ、早めに知って安心して進めましょう。
【2025年最新版】相続手続きの基本的な流れ

相続が発生すると、遺族は突然たくさんの手続きに直面します。
「いつ何をすればいいの?」「誰に相談すべき?」と迷うことも多いですよね。
この章では、相続手続きのスタート時期から、全体の流れを初心者にも分かりやすく解説します。
相続の基本フローを知ることで、後回しにしてしまいがちな準備もスムーズに対応できるようになります。
特に、相続税の申告や名義変更などには期限や提出書類のルールがあるため、早めの把握が重要です。
ここでしっかり流れをつかんで、「あとから困らない」ための一歩を踏み出しましょう!
1-1. 相続手続きはいつから始める?適切なタイミングを解説
実は、相続手続きには「始めるべきタイミング」があるんです!
【チェックポイント】
- 死亡届の提出:7日以内
- 相続放棄の期限:3か月以内
- 相続税の申告期限:10か月以内
- 銀行口座の凍結解除には戸籍や遺言書が必要
→相続手続きは**「できるだけ早く、でも準備してから」**が基本。
葬儀が落ち着いた後、1か月以内にスケジュールを立てるのが理想的です!
1-2. 【完全ガイド】相続手続きに必要な書類一覧
「書類が多すぎて混乱しそう…」という方も安心してください。必要な書類はパターン化できます!
【主な必要書類】
- 被相続人の戸籍謄本・住民票除票
- 相続人全員の戸籍・印鑑証明書
- 遺言書(ある場合)
- 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書
- 預金・株式の残高証明書など
→事前にリストアップしておけば、効率的に集められます。
手続き先(金融機関・法務局・税務署)によっても必要書類は異なるので、確認を忘れずに!
1-3. 初めての方でもわかる!相続手続きの全体像と進め方
相続手続きの流れは、以下のようなステップで進めていきます!
【相続の流れ(簡易版)】
- 被相続人の死亡届を提出
- 相続人の確定(戸籍で確認)
- 財産の調査(不動産・預金・借金など)
- 遺言書の有無を確認
- 相続放棄や限定承認の判断(3か月以内)
- 遺産分割協議・遺言の執行
- 相続税の申告・納付(10か月以内)
- 不動産などの名義変更・登記手続き
→一度流れをつかめば、次に何をすればいいのか迷わず進められます!
チェックリストを作って、順番通りに取り組むのがおすすめですよ!
相続順位と法定相続人の確認方法
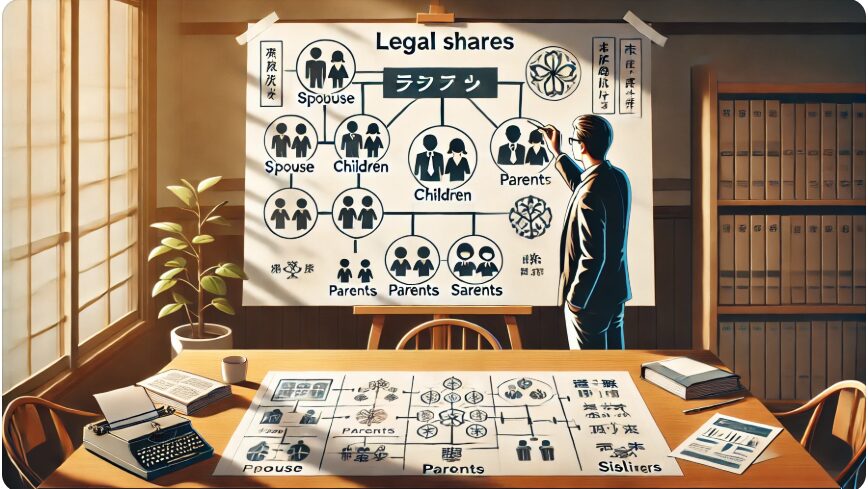
相続では「誰がどれだけ遺産を受け取るか」がとても重要なポイントになります。
しかし、法定相続人や相続順位のルールは複雑で、勘違いすると後々のトラブルの原因にも。
この章では、相続人の範囲や優先順位、兄弟姉妹の取り分などをわかりやすく整理しています。
遺産分割や手続きに入る前に、まずは“誰が相続の対象になるのか”を正確に理解しておきましょう。
配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など、ケースごとに異なるルールを図解で解説していますので、
「うちはどのパターン?」と気になった方は、ここからチェックを始めてください!
相続財産の範囲と評価方法
相続では、「何が財産に含まれるのか?」を正確に把握することがとても大切です。
現金や預貯金だけでなく、不動産や株式、車なども対象になるため、思った以上に範囲が広がることもあります。
この章では、相続の対象になる財産の種類と、それぞれの評価方法を具体的に解説します。
評価額は相続税にも大きく関わるので、税務署がチェックする基準やポイントを事前に知っておくことが重要です。
とくに不動産は評価が難しく、固定資産税評価額や路線価など専門的な計算も必要になります。
ここでしっかり知識を得て、納税や分割で損をしない相続準備を進めましょう!
2-1. 法定相続人とは?誰が相続できるのかを解説
「そもそも誰が相続人になるの?」と疑問に思う方、多いですよね。
【法定相続人に該当する人】
- 配偶者(常に相続人になる)
- 子ども(いない場合は直系尊属=親)
- 親もいなければ兄弟姉妹
- 養子や認知された子どもも対象になる
→誰が相続人になるかは、民法で明確に決まっているんです!
まずは戸籍を取り寄せて、法定相続人の確認から始めましょう。
2-2. 【図解】相続順位の具体的な規定と計算方法
実は、相続には“優先順位”があるんです!
【相続順位のルール】
- 第一順位:子ども(配偶者と2分の1ずつ)
- 第二順位:親(子どもがいない場合)
- 第三順位:兄弟姉妹(親もいない場合)
【計算例】
- 配偶者と子2人 → 配偶者1/2、子1人あたり1/4ずつ
- 配偶者と親 → 配偶者2/3、親1/3
→順位と人数によって割合が変わるので注意!
財産分割の前に、誰がどのくらいの割合かをしっかり把握しておきましょう。
2-3. 兄弟姉妹の相続割合は?知っておくべきルール
「兄弟にも相続権ってあるの?」…実はあります!
【兄弟姉妹が相続人になるケース】
- 子どもも親もいない場合
- 配偶者がいる場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
【注意点】
- 異母兄弟・異父兄弟も相続対象
- ただし、代襲相続できるのは“兄弟の子”まで
→兄弟姉妹は第三順位であることを覚えておきましょう。
複雑な家族構成の場合は、戸籍でしっかり確認するのが大切です。
相続財産の範囲と評価方法
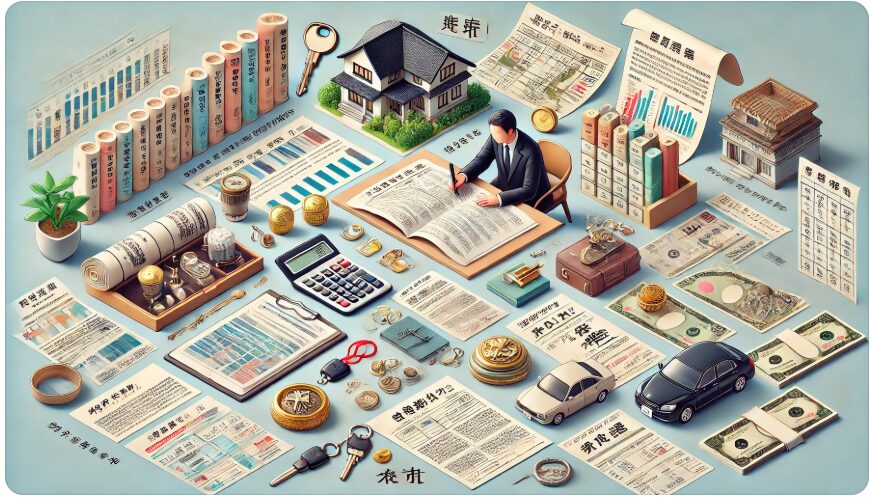
相続では、「何が財産に含まれるのか?」を正確に把握することがとても大切です。
現金や預貯金だけでなく、不動産や株式、車なども対象になるため、思った以上に範囲が広がることもあります。
この章では、相続の対象になる財産の種類と、それぞれの評価方法を具体的に解説します。
評価額は相続税にも大きく関わるので、税務署がチェックする基準やポイントを事前に知っておくことが重要です。
とくに不動産は評価が難しく、固定資産税評価額や路線価など専門的な計算も必要になります。
ここでしっかり知識を得て、納税や分割で損をしない相続準備を進めましょう!
3-1. 相続の対象になる財産とは?現金・不動産・株式の扱い
相続される財産って、実はかなり幅広いんです!
【相続の対象になる財産】
- 現金・預金
- 不動産(家・土地)
- 株式・投資信託・仮想通貨
- 自動車・貴金属
- 借金(債務)も相続対象に含まれる!
→「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も引き継ぐ点に注意。
まずは財産目録を作成して、全体像を把握しましょう。
3-2. 相続財産の評価基準【税務署がチェックするポイント】
「財産の評価ってどうやるの?」という疑問、ありますよね。
【評価の基本ルール】
- 現金・預金:残高ベースで評価
- 株式:相続時の時価または平均値
- 不動産:固定資産評価額 or 路線価方式
【税務署が見るポイント】
- 評価額の妥当性
- 過小申告がないか
- 負債や非課税財産の正しい記載
→評価がズレると税額が大きく変わるので慎重に!
不安な場合は、税理士に相談するのも手です。
3-3. 不動産の評価方法と具体的な計算例
不動産評価は、ちょっとややこしいですよね。
【主な評価方法】
- 路線価方式:市街地の土地が対象(国税庁HPで調べられる)
- 倍率方式:路線価がない地域で適用
- 建物は「固定資産税評価額」を使う
【例:土地100㎡・路線価20万円の場合】
20万円 × 100㎡ = 2,000万円
→「実際の売却価格」ではなく、「評価額」で判断するのがポイント!
相続税の申告に必要なので、書類と一緒にきちんと保管しておきましょう。
相続税の計算と申告の流れ
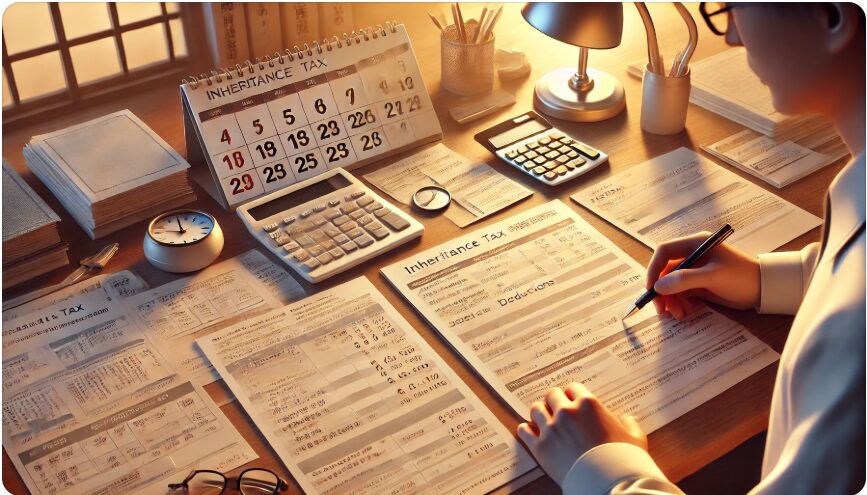
相続が発生したら避けて通れないのが「相続税の計算と申告」ですよね。
税金の知識がないと「どれくらいかかるの?」「いつまでに払うの?」と不安になる方も多いです。
この章では、相続税の計算方法から、申告・納付までの具体的な流れをやさしく解説します。
特に重要なのが、基礎控除や配偶者控除などの節税ポイントを理解しておくこと。
「損しない相続」を実現するためには、税額の正しい把握と期限内の対応が欠かせません。
このパートを読むことで、相続税への不安がグッと軽くなるはずです!
4-1. 相続税の計算方法【控除を活用して節税する方法】
「相続税ってどうやって計算するの?」と感じたら、まずは基本の流れを押さえましょう!
【相続税の計算ステップ】
- 相続財産の総額を計算
- 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を差し引く
- 課税対象額をもとに税率を適用
- 各人の取得額に応じて按分
【節税に使える控除】
- 配偶者控除(最大1億6,000万円まで非課税)
- 小規模宅地等の特例(最大80%評価減)
→正しい控除の適用が、節税の最大のカギ!
事前のシミュレーションがとても重要です。
4-2. 相続税の申告と納付の流れ【期限を守るためのポイント】
実は、相続税にはしっかりと期限があります!
【申告・納付の基本】
- 相続開始(死亡)から10か月以内に申告&納付が必要
- 税務署に「相続税申告書」を提出
- 納税は原則“現金一括”が原則(延納・物納もあり)
【注意点】
- 遅れると「延滞税」「加算税」が発生
- 納税資金の確保を早めに検討する
→期限ギリギリの申告はトラブルのもと!
早めに準備しておくと安心ですよ。
4-3. 相続税の基礎控除とは?適用条件と計算例
「相続税がかかるのは一部の人だけ」って聞いたことありませんか?
【基礎控除の内容】
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数
- たとえば相続人が2人なら → 4,200万円まで非課税
【計算例】
遺産総額:5,000万円
法定相続人:2人
基礎控除:3,000万+600万×2=4,200万円
課税対象:5,000万-4,200万=800万円
→相続税のかかる・かからないラインを把握しておくと対策しやすい!
自分に必要か迷ったら、簡易シミュレーターも活用を!
遺産分割協議の進め方

相続手続きで最もトラブルが起こりやすいのが「遺産分割協議」です。
相続人同士で遺産の分け方を話し合う場ですが、意見が合わずに揉めるケースも少なくありません。
この章では、遺産分割協議の基本とスムーズに進めるためのポイントをわかりやすく紹介します。
また、遺言書がある場合の流れや、相続放棄の手続きについても詳しく解説。
「話し合いが不安…」「遺言があるけどどう使えばいい?」という方にも役立つ内容です。
しっかりと準備と理解をしておくことで、相続人全員が納得できる協議が実現できますよ!
5-1. 遺産分割協議とは?スムーズに進めるためのポイント
「遺産分割協議って、何を話し合うの?」と思う方も多いはず。
【協議の目的】
- 相続人全員で遺産の分け方を決める会議
- 書面(遺産分割協議書)で合意内容を残す必要あり
- 全員の同意がないと無効
【スムーズに進めるコツ】
- 事前に財産目録を共有
- 第三者(専門家)を交える
- 感情的にならず、ルールベースで判断
→「冷静な話し合い」と「書面化」が成功のカギ!
感情に流されず、公平性を意識しましょう。
5-2. 遺言書の活用とその重要性【遺言がある場合の流れ】
「遺言書があれば協議は不要?」…実はそうとも限りません。
【遺言書がある場合の流れ】
- 検認手続き(公正証書遺言は不要)
- 遺言に従って分割を進める
- 相続人が納得しない場合は協議も可能
【遺言書のメリット】
- 争いを未然に防げる
- 遺志を明確に伝えられる
- 節税効果があるケースも
→遺言書は“相続トラブル防止の最強ツール”!
元気なうちに作成しておくのがおすすめです。
5-3. 相続放棄の方法とその手続き【放棄すべきか判断する基準】
「借金の相続はしたくない!」というときは放棄が選択肢です。
【相続放棄の基礎知識】
- 家庭裁判所に申述
- 相続開始から3か月以内に手続きが必要
- 他の相続人の取り分が増える場合もある
【放棄すべきかの判断基準】
- 財産より借金が多い
- 相続関係が複雑で関わりたくない
- 放棄による不利益がないか事前確認
→「放棄すればすべての相続権を失う」点に注意!
判断に迷ったら弁護士や司法書士に相談しましょう。
不動産の名義変更の手続き
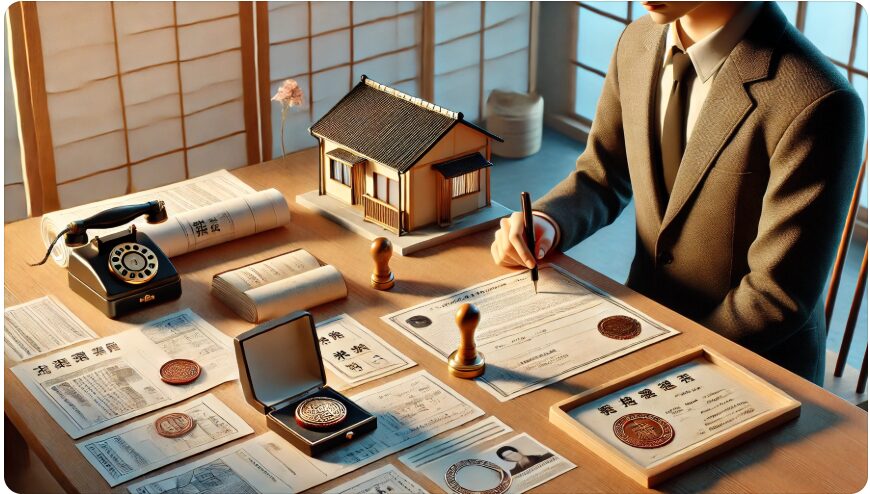
相続において不動産が含まれる場合、避けて通れないのが「名義変更」の手続きです。
名義をそのままにしておくと、売却や融資ができなかったり、相続人間でのトラブルにつながることも。
この章では、土地や建物の名義変更をスムーズに進めるための流れや必要書類を詳しく解説します。
特に法務局での登記申請は、準備不足だと何度も足を運ぶことになりかねません。
費用の目安や手続きにかかる期間もあわせて紹介するので、手続きにかかる全体像をつかむのにぴったりです。
**「早めの準備が安心につながる」**ことを、このパートでしっかり理解しておきましょう!
6-1. 土地・建物の名義変更をスムーズに行う方法
不動産の相続では「名義変更」がとても大切です!
【名義変更の基本手順】
- 相続人を確定する
- 遺産分割協議書を作成
- 登記申請書を作成し、法務局に提出
- 登記完了後、法務局から完了通知が届く
【スムーズに進めるコツ】
- 必要書類は事前にチェック
- 協議書は全員の実印+印鑑証明が必要
- 不備が出ないように司法書士へ相談するのも◎
→登記をしないと売却や担保設定ができません。
「名義変更は相続のゴール」と思って進めましょう!
6-2. 法務局での登記手続きの流れと必要書類
「法務局って何をするの?」と不安な方へ。
【登記申請の流れ】
- 書類一式を用意し、法務局へ提出
- 審査期間:約1〜2週間
- 問題がなければ名義変更が完了
【必要書類】
- 相続人の戸籍・住民票
- 被相続人の除籍謄本
- 遺産分割協議書(or 遺言書)
- 登記申請書+登録免許税
→書類に不備があると、やり直しになります。
「事前確認」と「コピーの控え保存」が安心のポイント!
6-3. 不動産登記にかかる費用と手続きの期間
気になるのが、「いくらかかるの?」という費用面ですよね。
【主な費用項目】
- 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
- 司法書士報酬:5万円〜10万円前後
- 書類取得費用(戸籍・住民票など)
【手続き期間】
- 書類収集:約1〜2週間
- 登記処理:約1〜2週間
- トータル:約1ヶ月が目安
→早めにスケジュールを組んで動くのが大事!
費用が不安なら、見積もりだけでも司法書士に相談してOKです。
相続にかかる費用と節約のコツ
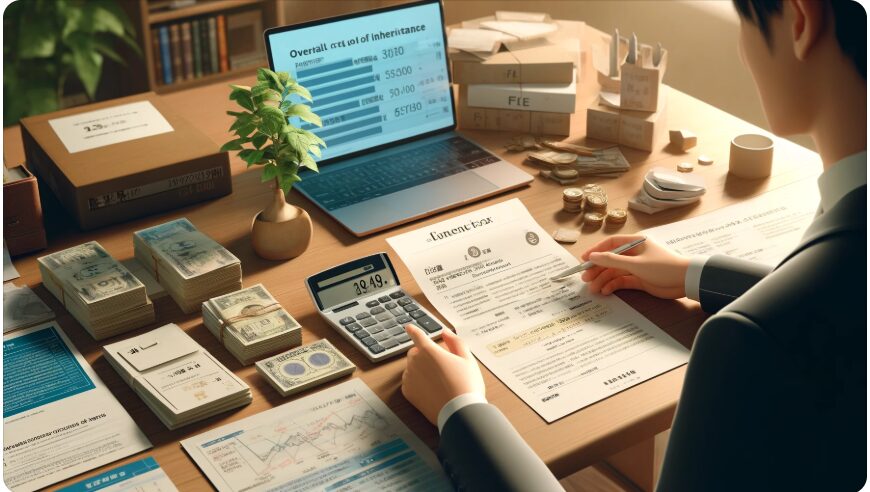
相続手続きでは、「どのくらい費用がかかるの?」という疑問がつきものです。
実は、相続税だけでなく、登記費用や専門家への報酬などさまざまな費用が発生します。
この章では、相続にかかる費用の全体像をわかりやすく整理し、少しでも出費を抑えるコツをご紹介します。
弁護士・税理士・司法書士などに依頼する際の相場感も把握しておくと安心です。
また、節税につながる控除の活用や、相続税額の簡易シミュレーション方法も紹介。
無駄な出費を避けながら、必要なコストを見極めるポイントをぜひチェックしてください!
7-1. 相続にかかる基本的な費用一覧【相続税・手続き費用】
相続では、実は想像以上にお金がかかることも。
【主な費用の内訳】
- 相続税(課税対象者のみ)
- 登録免許税(不動産登記)
- 戸籍・住民票の取得手数料
- 専門家への報酬(弁護士・司法書士など)
- 遺産分割協議書の作成費用
→費用は“発生時期”もさまざまなので、一覧で管理しておくと安心!
事前に資金繰りのシミュレーションもおすすめです。
7-2. 弁護士・司法書士に依頼するときの費用相場
「専門家に頼むと高そう…」そんなイメージありますよね?
【おおよその相場感】
- 司法書士:5万〜15万円(登記手続き代行)
- 弁護士:30万〜100万円(トラブル対応や協議代理)
- 税理士:10万〜30万円(相続税の申告)
【節約のポイント】
- 内容がシンプルなら司法書士だけでOK
- 相見積もりを取ることでコストを比較可能
- 「初回相談無料」の専門家も多い!
→自分に必要なサポートを見極めて、ムダなく依頼しましょう。
7-3. 相続税の具体的な税額シミュレーション
実際、「自分がいくら払うのか」が気になりますよね。
【シミュレーション例】
- 遺産:1億円
- 相続人:配偶者+子ども1人
- 基礎控除:3,000万+600万×2=4,200万円
- 課税対象:1億−4,200万=5,800万円
- 税率:15%+α(控除あり)
→シミュレーションサイトや税理士による無料相談も活用すると便利!
事前に数字を把握することで、節税策や準備の質も変わります。
相続手続きの期限と注意点
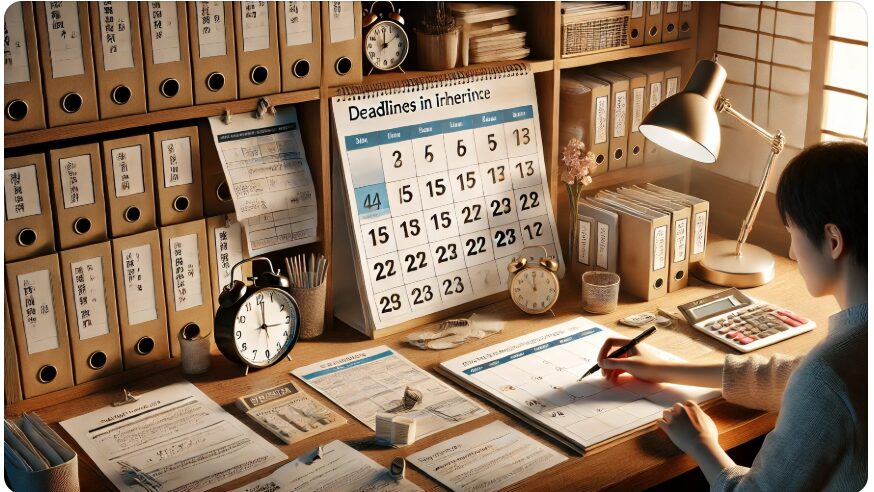
相続手続きには、実は厳格な「期限」があるのをご存じですか?
期限を過ぎてしまうと、延滞税が発生したり、不利な状況になってしまうことも。
この章では、相続手続きを開始してから完了するまでに気をつけたいスケジュールや注意点を解説します。
特に相続税の申告・納付は“10ヵ月以内”と期限が決まっているため、早めの行動がカギになります。
さらに、期限内に完了するためのスケジュール管理法や事前準備のコツも紹介していますので、
「うっかり手続きが遅れた…」と後悔しないために、ぜひこのパートで対策を立てておきましょう!
8-1. 相続手続きを開始してからの期間【早めの対応が重要】
「相続って、いつから手続きすればいいの?」と迷いがちですよね。
【目安となる主な期限】
- 死亡届の提出:7日以内
- 相続放棄・限定承認:3か月以内
- 準確定申告:4か月以内
- 相続税申告・納付:10か月以内
→期限を逃すとペナルティや手続き拒否のリスクも!
まずは死亡後1か月以内に全体のスケジュールを立てることが大切です。
8-2. 相続税の申告・納付の期限【延滞税を防ぐ方法】
「10か月以内に申告・納付」と聞いても、意外とあっという間です!
【期限を守るためのポイント】
- 死亡日を起点にカウント
- 相続人の確定・財産調査は早めに
- 財産目録や評価額が出たらすぐに申告準備
- 延納や物納が必要な場合も早めに申請を
→納税資金の準備が間に合わず、延滞税がかかる人も多いです。
資金繰りも含めて、早期に動くのが成功の秘訣!
8-3. 期限内に手続きを終わらせるためのスケジュール管理
「やること多すぎて、間に合わない…」そんな心配を解消しましょう!
【おすすめスケジュール管理法】
- 1か月目:戸籍収集・相続人確定
- 2か月目:財産の洗い出し・目録作成
- 3か月目:相続放棄の判断
- 4〜6か月目:遺産分割協議・登記準備
- 7〜10か月目:相続税申告・納税・名義変更
→タスクを「今やること」「今月やること」に分けて管理するのがコツ!
無料のエクセルテンプレートやアプリを活用しても便利です。
相続トラブルを防ぐ方法と対策

相続の場面で実は多いのが、「家族間のトラブル」です。
話し合いがもめたり、遺産の分け方で感情的な対立が起こるケースも少なくありません。
この章では、よくある相続トラブルの事例や、その解決策・予防策をわかりやすく紹介します。
特に、遺言書の活用はトラブル防止に非常に効果的です。
また、問題が大きくなる前に弁護士に相談すべきタイミングやポイントも押さえておきましょう。
「円満な相続」を実現するために、今のうちからできる備えを始めておくことが大切です!
9-1. よくある相続トラブル事例とその解決策
相続では、意外と**「家族なのに揉める」**ケースが多いんです!
【よくあるトラブル例】
- 遺産分割で兄弟が対立
- 財産の使い込み疑惑
- 相続人の1人が連絡に応じない
- 不公平な遺言書の存在
【主な解決策】
- 弁護士など第三者を介入させる
- 相続調停の申立て(家庭裁判所)
- 冷静な話し合いと証拠の整理が重要!
→感情に流されず、事実と法律で進めることが大切です。
9-2. 相続トラブルを回避するための事前対策【遺言書の活用】
「うちは大丈夫」と思っていても、念のための対策はしておきたいですよね。
【トラブルを防ぐ対策】
- 公正証書遺言の作成
- 相続人全員への情報共有
- 生前贈与や生命保険の活用
- 財産目録の作成・保管
→遺言書は“争族”を避ける最大の予防策!
特に不動産がある家庭では、早めの準備が効果的です。
9-3. 相続トラブルが起きた場合の弁護士相談のタイミング
「揉め始めたけど、どこまで自分で対応すれば…?」と悩んだら、早めに専門家へ。
【弁護士に相談すべきタイミング】
- 話し合いが平行線のとき
- 特定の相続人が独断で進めている場合
- 不公平な分配を強いられている
- 相手が代理人を立ててきた
→我慢しすぎず、“不安を感じた時点”で無料相談を活用しましょう。
早期相談=早期解決につながるケースがほとんどです。
結論|相続手続きを知れば、迷わずスムーズに対応できます!
**相続手続きは「何から始めればいいのか分からない」という不安がつきものです。**この記事では、手続きの流れ・必要書類・税金・費用・トラブル対策までを網羅的に解説しました。
特に重要なのは、**期限と書類の準備を早めに進めること。**スケジュールを立て、法定相続人や相続財産の確認を行いましょう。遺言書がある場合は優先して確認し、遺産分割協議や不動産登記なども早めの対応がカギです。
さらに、**相続税の節税ポイントや費用の節約法も知っておくことで、大きな損を防ぐことができます。**弁護士や専門家の活用も有効ですので、無理せずプロの手を借りる判断も大切です。
👉 「この記事の内容を実践すれば、相続の不安を減らし、安心して手続きを進められます!」
まずは、相続人・財産・期限をリストアップするところから始めてみましょう!
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

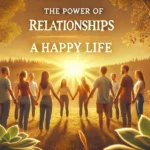

コメント