最近、SNSを通じた投資詐欺の被害が急増しています。特に高齢者をターゲットにした手口は巧妙化しており、「必ず儲かる」「著名人も推奨」といった誘い文句で多くの人が騙されています。被害は数百万円規模にのぼるケースも珍しくなく、深刻な社会問題となっています。
本記事では、最新のSNS型投資詐欺の手口や注意点、被害を防ぐ具体策を徹底解説! 政府の対策や、金融庁・警察・弁護士など相談先情報も網羅しています。資産を守るために、今こそ正しい知識が必要です。
この記事を読むことで、自分や家族を守るための「実践的な防衛術」が身につきます!
SNS型投資詐欺とは?高齢者を狙う手口と被害実態
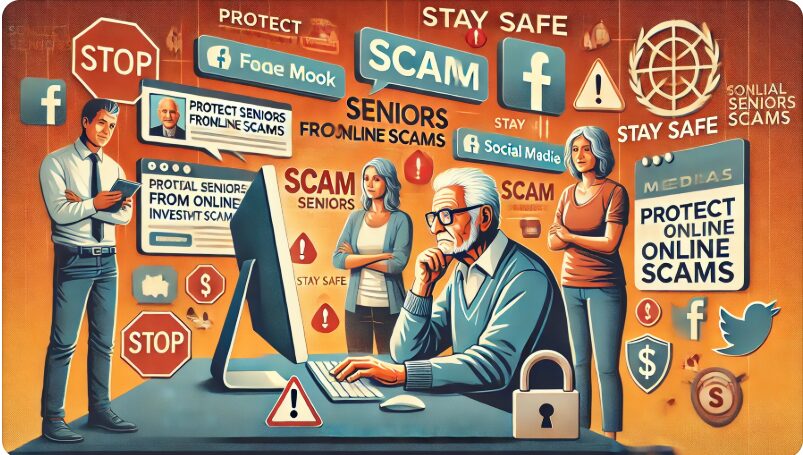
SNSの普及に伴い、投資詐欺も巧妙化しています。最近ではLINEやX(旧Twitter)、InstagramなどのSNSを使って高齢者に接近し、「簡単に稼げる」「初心者でも安心」などの甘い言葉で勧誘する手口が急増中です。
とくに高齢者は年金や退職金を狙われやすく、詐欺グループにとっては格好のターゲット。 被害者は「まさか自分が…」と感じるほど自然に騙されてしまうのが特徴です。
この記事では、SNS型投資詐欺の基本的な仕組みや誘導の流れ、なぜ高齢者が狙われるのか、そして実際の被害事例から見えてくる最新動向を解説します。
あなたやご家族を守るための第一歩として、ぜひご覧ください。
1-1: SNS型投資詐欺の基本構造と誘導プロセス
SNS型投資詐欺は、以下のような流れで進行します。
- SNSでの接触(DM・広告・フォロー)
- 「限定情報」や「利益確定」などの魅力的な話を提示
- LINEグループや投資セミナーへ誘導
- 架空の投資サイトやアプリへ登録させる
- 実際に入金させて出金不能になる
ここが重要!
最初から「投資しませんか?」とは言いません。
「信頼関係を築いたあとに一気に仕掛けてくる」のが典型的な手口です。
1-2: 高齢者が狙われる心理的スキを突く話術
「将来が不安ですよね?」「年金だけでは不安じゃないですか?」
こんな言葉にドキッとしたこと、ありませんか?
詐欺師は、高齢者のこうした孤独・老後不安・経済的不安につけ込んできます。
- 「これは特別な情報です」と優越感を与える
- 「あなたにだけ」と特別感を演出
- 「すでに他の人は利益を得ています」と焦りを煽る
つまり、感情に訴える話術を駆使して警戒心を下げてくるのです。
実はこうした話し方は、詐欺で最も使われる心理テクニックです。
1-3: 被害額急増データで見る最新動向
警察庁や消費者庁によると、SNS型投資詐欺の被害額は2023年から急激に増加しています。
📌【最新データの一例】
- 2023年:被害額 約600億円(前年比+150%)
- 被害者の約6割が60代以上
- 被害の7割が「LINE経由」で発生
ここが重要!
「スマホが苦手な人ほど狙われやすい」傾向にあるため、家族や周囲の協力も欠かせません。
SNSでの投資話には、まずは疑う目を持ちましょう!
最新投資詐欺トレンド2025|SNS勧誘・著名人利用の実例
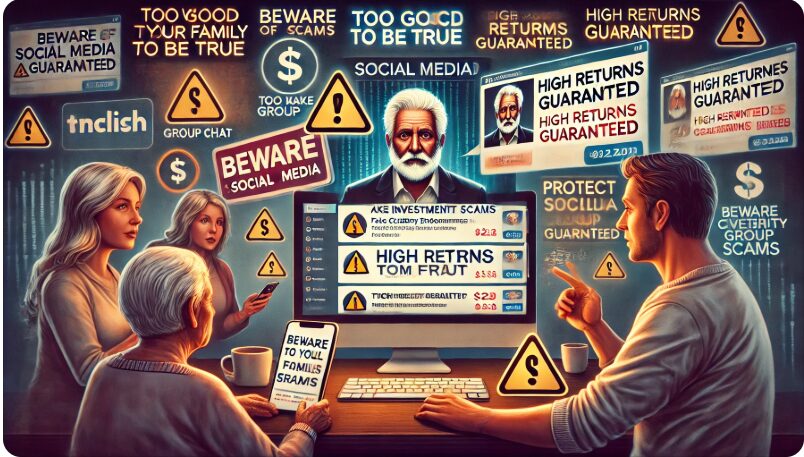
2025年の投資詐欺は、ますます巧妙かつ巧手になっています。中でも注目すべきは、SNSを悪用した投資勧誘の拡大と、著名人の偽アカウントを使った詐欺の激増です。
LINEやInstagram、X(旧Twitter)などを通じて、「○○さんも使ってる」「今だけ限定」などの言葉で信頼感を装い、被害者を誘導するケースが後を絶ちません。
さらに、2025年に実際に発生した詐欺事件の中には、大手メディアも報道した著名事件も多数あり、一般人だけでなく有名人の信頼性すら利用されています。
本章では、最新トレンドの手口とその実例、実際に使われた勧誘文面や偽アカウントの特徴などを具体的に解説していきます。
2-1: LINE・X・Instagramで拡散する勧誘メッセージ
「こんにちは!投資のグループに興味ありませんか?」
こんなDM、見たことありませんか?
最近はSNS上で以下のような手口が横行しています:
- LINEで「初心者歓迎」と勧誘
- Instagramのコメント欄に「秘密の稼げる情報」
- X(旧Twitter)で「億り人続出」などのタグ投稿
ここが重要!
正規の金融機関や証券会社がDMで直接勧誘することはほぼありません。
SNSでの誘いには慎重になりましょう。
2-2: 2025年発生の代表的な投資詐欺事件レポート
2025年上半期には、以下のような事例が報告されています。
- X経由で海外FX業者に勧誘 → 1,200万円の損失
- LINEで「月利10%」と謳う仮想通貨案件 → 出金停止被害
- Instagramで著名人を騙ったアカウントがNFT販売 → 偽アプリで資金消失
実際、消費者庁の報告では2025年上半期だけで被害額は約350億円超。
「そんなの引っかからないよ」と思っていても、
巧妙な演出と心理戦で冷静さを失ってしまう人が少なくありません。
2-3: 芸能人・著名人の偽アカウント利用ケース
特に注意したいのが、著名人の偽アカウントです。
たとえば:
- 有名経済評論家のアイコンと名前でDM送信
- 芸能人が「〇〇投資で成功」と投稿(実は偽物)
- YouTube広告で本人の映像を合成した詐欺動画
ここが重要!
認証マーク(✔)の有無や、フォロワー数、投稿の一貫性をチェックしてください。
公式とそっくりでも、プロフィール欄のリンクが詐欺サイトというケースが多発しています。
ロマンス詐欺×投資勧誘の合わせ技を防ぐ方法
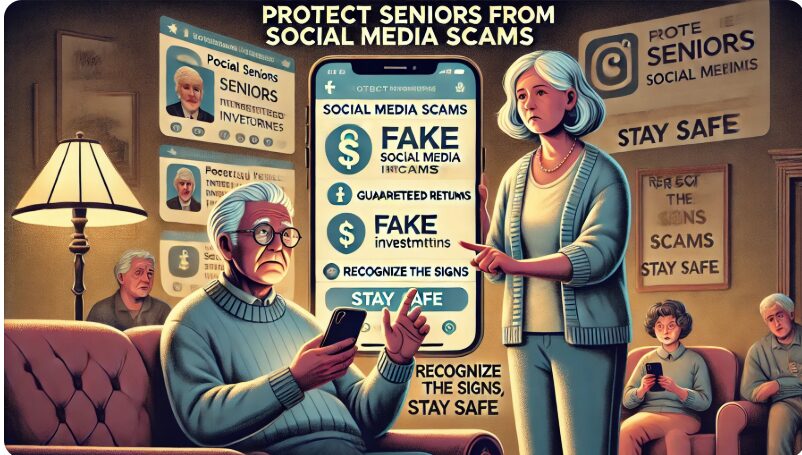
最近急増しているのが、**ロマンス詐欺と投資詐欺を組み合わせた「合わせ技型詐欺」**です。
SNSやマッチングアプリで親密な関係を築いた後、「あなたの将来を思って…」と投資を勧められるケースが多く、恋愛感情に乗じて金銭をだまし取られる被害が全国で報告されています。
特に高齢者は、「本気で愛されている」と信じてしまい、大金を送金してしまうリスクが高いのが現状です。
この章では、典型的な詐欺の特徴、家族や友人が気づくためのサイン、そして送金前にできる自衛策や相談窓口をわかりやすく解説します。
3-1: 国際ロマンス詐欺の特徴と恋愛感情の悪用
「海外在住の軍人」「高収入の医師」など、魅力的な人物からメッセージが届く――
実は、それがロマンス詐欺の始まりです。
典型的な流れは:
- SNSで知り合い、優しい言葉で距離を縮める
- 「日本で一緒に住みたい」など将来を匂わせる
- 「トラブルがありお金が必要」と送金を依頼
- 投資話に発展、「一緒に増やそう」と誘導
感情に訴えることで、判断力を奪うのが狙いです。
3-2: 家族・友人ができる早期発見チェックリスト
大切な人が被害にあわないよう、家族や友人も気をつけたいですね。
以下のような行動があれば、要注意です!
✅ スマホを頻繁に見てニヤニヤしている
✅ 「新しい友達ができた」と急に恋愛の話をする
✅ 見たことないアプリや仮想通貨の話をし出す
✅ 「誰にも言わないで」と言ってくる
✅ 海外からの送金指示がある
ここが重要!
普段と違う行動があれば、「ちょっと気をつけて」と声をかけてください。
3-3: 金銭送金前に使える相談窓口とブロック術
もし少しでも怪しいと感じたら、一人で判断せずに相談することが大切です。
📌 相談先例:
- 消費者ホットライン:188
- 警察相談専用電話:#9110
- 金融庁 金融サービス利用者相談室
- 各都道府県の消費生活センター
また、相手がSNS上であれば:
- ブロック+報告機能を活用する
- LINE・Instagramの「通報ボタン」で情報提供
「送金する前に、相談する」
これが被害を未然に防ぐ一番の方法です!
SNS勧誘で要注意の兆候とブロック・通報テクニック

SNSを使った投資詐欺は、最初は親しみやすいメッセージから始まるのが特徴です。
「必ず儲かる」「この情報はあなただけに」といった甘い言葉に注意が必要。特に高齢者は、信頼感を巧みに演出するプロフィールやリンクに騙されやすくなります。
でも、騙される前に気づけるポイントは意外とシンプルなんです!
この章では、怪しいアカウントの見分け方・すぐに実行できるブロックや通報の方法、そして個人情報を求められた時の断り文例を丁寧に解説します。
SNSでの自衛力を高めることで、あなたの資産と安心をしっかり守りましょう。
4-1: 怪しいプロフィール・リンクの見破り方
詐欺アカウントの特徴は意外と単純。以下のポイントを見逃さないでください!
✅ プロフィール画像が美男美女/著名人風
✅ フォロワー数や投稿に違和感(少なすぎor多すぎ)
✅ URL付きの怪しいDMが突然届く
「なんか怪しいな…」と感じたら、絶対にURLをクリックしないこと!
まずは検索エンジンでその名前やリンクを調べてみると良いですよ。
4-2: 「必ず儲かる」誘い文句への即時対応策
「月利20%保証!」「100%儲かる」なんて言葉、怪しすぎですよね。
でも、実際は丁寧な口調で近づいてくるので、詐欺と気づかない人も多いんです。
🔸こんな誘い文句は要注意:
- 「金融庁に登録してます(←嘘)」
- 「他の人も大成功してるから安心」
- 「今だけのチャンス!」
即ブロック&通報しましょう。 少しでも迷ったら、誰かに相談を!
4-3: 個人情報・資金要求に対する拒否テンプレート
「口座番号を教えて」「暗号資産を送って」なんて言われたら…アウトです。
以下のような断りテンプレートを使って毅然と対応しましょう。
📌例:
「申し訳ありませんが、個人情報や資金の提供はいたしかねます。」
「信頼できる情報源で確認してから判断します。」
その後は迷わずブロック&通報を。感情的にならず、冷静な対応がカギです!
金融庁・専門家が教える詐欺業者の見分け方&相談先
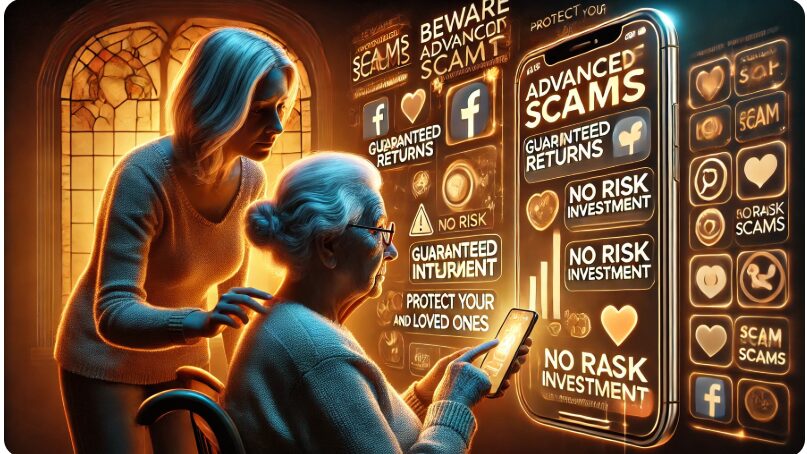
SNS型投資詐欺に巻き込まれないためには、正しい知識と信頼できる情報源を持つことが最大の武器になります。
金融庁や国民生活センターは、定期的に詐欺に関する注意喚起を発信しており、公式サイトで最新の警告や相談先が確認可能です。また、実際に被害を受けた方の中には、弁護士に相談することで返金交渉が進んだケースもあります。
さらに、障がいを持つ投資家に特化した支援サービスも存在しており、安心して資産を守る仕組みが整ってきています。
この章では、信頼できる機関・専門家がどのように詐欺業者を見分けているのか、実践的なアドバイスと相談窓口の情報を詳しくご紹介します。初心者やご高齢の方も、この知識を備えておけば詐欺に怯える必要はありません!
5-1: 金融庁・国民生活センターの最新注意喚起
金融庁や消費者庁は、公式サイトで詐欺の手口や相談方法を随時更新中。
- 金融庁「無登録業者リスト」
- 国民生活センターの「相談窓口一覧」
- LINEなどSNS業者への通報ガイド
詐欺業者は登録なしの違法営業が多い!
まずは公式サイトで「業者名を検索」してみましょう。
5-2: 弁護士が語る詐欺業者の共通パターン
多くの弁護士が語る「詐欺業者あるある」は以下の通り:
- 運営会社の実態が不明
- 電話番号や所在地が曖昧
- 返金保証などの“うますぎる条件”を提示
「怪しいな」と思ったら、消費者相談や無料の法律相談を利用しましょう。
専門家に相談するだけで、冷静になれるケースも多いです。
5-3: 障がいのある投資家を守る支援サービス一覧
詐欺業者は、障がいや高齢者を「狙いやすいターゲット」と見なしています。
ですが、そんな方を守る公的支援もちゃんと整っています!
✅ 成年後見制度(本人の代わりに財産管理)
✅ 消費者ホットライン(188)
✅ 障害者就業・生活支援センター
「家族に頼れない…」という方でも大丈夫。
自治体の福祉課や専門支援窓口へ早めに相談してください。
政府・警察・業界団体の最新対策と法改正ポイント

SNS型投資詐欺の被害拡大に対して、政府・警察・金融業界が連携して対策を強化しています。
最近の金融商品取引法の改正では、詐欺行為に対する罰則が厳格化され、違法な投資勧誘を抑止する枠組みが整備されました。また、警察や自治体による特殊詐欺の撲滅キャンペーンも全国で活発化しており、地域ぐるみでの啓発活動が進んでいます。
加えて、X(旧Twitter)やInstagramなどSNSプラットフォームも、不審なアカウントの凍結・通報システムを強化中。通報フローも簡素化され、一般ユーザーが詐欺情報を迅速に報告できるようになっています。
この章では、法改正のポイントと現場での具体的対策をわかりやすく解説します。最新動向を知っておくだけでも、詐欺に巻き込まれるリスクを大幅に減らせます!
6-1: 金融商品取引法改正で強化された罰則ポイント
2023年以降、金融商品取引法が何度も改正されており、無登録業者への規制が大幅に強化されています。
✅ 無登録で投資勧誘した場合の刑罰が重くなった
✅ 虚偽の広告を出した業者に即時処分が可能
✅ 海外業者でも日本人勧誘に法的リスクが発生
つまり、「海外だから大丈夫」なんていうのは完全に嘘です。
法律はしっかり追いついてきています!
6-2: 警察・自治体の特殊詐欺撲滅キャンペーン
地域レベルでも、詐欺防止の動きが活発です。
📌 例:
- 各地の警察署が「防犯講座」や「詐欺撃退マニュアル」を配布
- 自治体が高齢者宅に詐欺対策ステッカーや録音機能つき電話機を配布
- 地域包括支援センターと連携し定期的な見守り訪問
実は、こうした施策で「被害を未然に防いだ」事例も多数あるんです!
6-3: SNS運営会社によるアカウント凍結・通報システム
SNS側も、「通報機能」や「詐欺検出AI」を強化中。
🔍 具体的には:
- Instagram:不審なDMの自動フィルター
- LINE:公式アカウントでの注意喚起・ブロック手順の配信
- X(旧Twitter):スパム報告が一定数超えると自動凍結
通報は1件でも有効です。
見かけたら「面倒」と思わず、社会全体の防御力を上げる行動をしてみましょう!
高齢者が安心して資産を守る投資ガイドライン

SNS型投資詐欺が急増する中、高齢者が資産を安全に守るための投資ガイドラインが今、大きな注目を集めています。
まず大前提として、「金融庁登録業者かどうか」を確認することが信頼の第一歩です。そして資産運用では、ハイリスクな商品ではなく、低リスクかつ分散された商品を選ぶのが基本。安全性を重視した資産形成が、老後の安心に直結します。
さらに、万が一詐欺に遭った場合にも、適切な相談機関や弁護士に早めに連絡することが被害の拡大を防ぐ鍵になります。
この章では、高齢者が騙されず、着実に資産を守っていくための具体的な方法を解説していきます!
7-1: 登録業者検索で確認する金融庁認可の有無
まず基本!
投資の勧誘を受けたら、必ず「登録業者かどうか」を確認してください。
✔ 金融庁「登録業者リスト」検索ツールを使う
✔ 登録番号・社名・代表者名を照合する
✔ 一致しなければ即NG!
「認可されてるって言ってたから安心」ではダメ。
必ず公式で確認しましょう。
7-2: 低リスク商品・分散投資で守る資産形成
詐欺に遭いやすい人の多くは、「一発逆転」を狙っています。
でも、**資産形成の王道は「長期・分散・低リスク」**です。
✅ つみたてNISA・iDeCoなどの制度を活用
✅ 複数の商品に分散投資
✅ 高金利の謳い文句には手を出さない
“増やす”より“守る”ことが大切。
シンプルで手堅い運用が一番安心です。
7-3: 被害後の返金交渉と弁護士依頼の流れ
もし被害にあってしまったら、泣き寝入りせずすぐに行動しましょう!
📌 対応フロー:
- 警察に被害届を提出
- 消費生活センターに相談(188番)
- 金融ADR制度の利用(仲介による返金交渉)
- 弁護士に依頼して損害賠償請求(法テラスで無料相談も可能)
早ければ早いほど返金率も高まります。
被害に気づいた瞬間から、時間との勝負です!
要注意金融商品:未公開株・社債・暗号資産のリスク
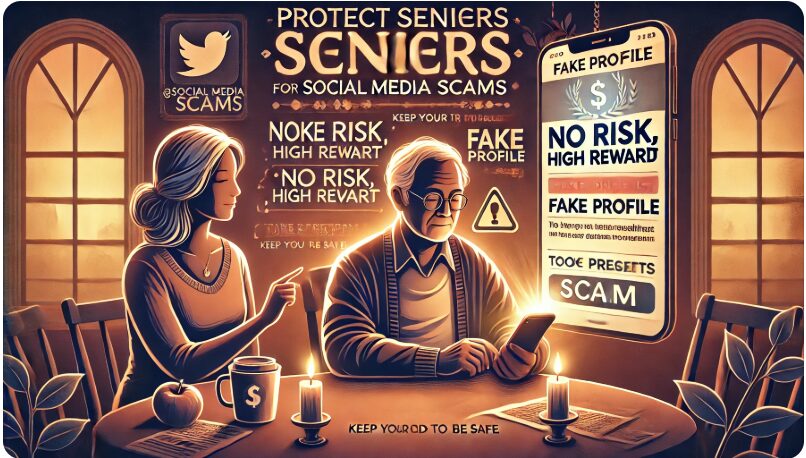
投資初心者や高齢者を狙った詐欺の中でも、特に注意が必要なのが「未公開株」「社債」「暗号資産(仮想通貨)」「NFT」といった高利回りをうたう金融商品です。
「今しか買えない」「必ず儲かる」といった誘い文句には要注意。未公開株や社債には流動性の低さや発行体の信頼性の不透明さといった重大なリスクが潜んでいます。また、暗号資産やNFTは仕組みが複雑で、詐欺業者が「新しい技術」や「ブロックチェーン」を装って巧妙に近づいてきます。
この章では、よくある詐欺シナリオや安全な口座の選び方を具体的に紹介し、リスクを避けるための判断軸をわかりやすく解説します。
8-1: 未公開株・社債の高利回りトークの危険度
「上場予定の未公開株です」「この社債は年利10%以上」といった話、よく聞きませんか?
でも、実はこれほとんどが詐欺です。
- 未公開株は売却先が存在せず換金できないことが多い
- 高利回りを保証する社債は、実態のない会社が発行しているケースも
金融庁の登録があるか確認するだけで多くの被害は防げます!
8-2: 仮想通貨・NFT投資詐欺の典型的シナリオ
仮想通貨やNFTは正しく使えば便利な資産ですが、詐欺の温床にもなっています。
典型的な手口はこちら:
- SNSで知り合った人が「確実に儲かる」と誘導
- 海外の取引所へ送金 → 出金できずに音信不通
- アートやトークンを高額で買わせるが価値なし
「利回り保証」「著名人の推薦」など、うますぎる話は99%詐欺です!
8-3: 安全な証券口座・ウォレット選びのチェック項目
投資を始めるなら、まずは「安全な環境作り」から。
チェックポイントはこちら:
- 金融庁登録のある証券会社を選ぶ
- ウォレットは二段階認証付きのものを使う
- パスワードは複雑に設定し、使い回さない
- 運営会社の実在性を調べる(HP・法人番号など)
ここがポイント! 安全な環境なら、詐欺に巻き込まれる確率はぐっと下がります。
SNS利用時の自衛策|プライバシー設定と情報リテラシー

SNSを利用する際、詐欺被害に遭わないためには「情報リテラシー」と「プライバシー設定」の強化が欠かせません。パスワードの管理が甘いだけでも、個人情報の流出やアカウント乗っ取りのリスクが高まります。
さらに、SNS上には信頼性の低い投資情報や詐欺的なリンクがあふれており、見極める力(ファクトチェック能力)も必要不可欠です。「儲かる話」には裏があるという前提で、冷静に判断することが重要ですね。
この章では、SNSの設定で今すぐできる対策や、怪しい投稿の見分け方、情報の真偽を確かめるコツをわかりやすく解説していきます。
9-1: 二段階認証・強力パスワードでSNSを守る
SNSの乗っ取り被害、増えてますよね。
今すぐやるべき対策はこれ:
- 二段階認証をオンにする
- パスワードは英数字+記号で10文字以上
- 過去に使ったパスワードはNG!
スマホで設定できるので、数分で詐欺リスクを大幅にカットできます!
9-2: 投資情報の真偽を3ステップでファクトチェック
怪しい投資情報、見たことありませんか?
確認のステップはこの3つ:
- 金融庁や証券取引等監視委員会のHPで確認
- Googleで詐欺報告がないか検索
- SNSのフォロワー数や過去投稿も確認
「本当か?」と一度立ち止まるクセをつけるだけで、詐欺被害は激減します。
9-3: プライバシー設定・公開範囲の最適化ガイド
誰でも見られる投稿になっていませんか?
公開範囲を調整するだけで安全性は大幅アップします。
- 投稿は「友達のみ」「フォロワー限定」に
- プロフィールは必要最低限に
- 不審アカウントは即ブロック
身近な設定で、あなたの資産と安心を守りましょう。
結論
SNS型投資詐欺は年々巧妙化しており、高齢者を狙った被害は深刻さを増しています。 特にLINEやXなどのSNSを通じて勧誘されるケースや、著名人の偽アカウントを悪用した詐欺が増加中です。こうした背景から、家族での情報共有や金融庁認可の有無確認がますます重要になっています。
また、「必ず儲かる」「今だけのチャンス」といった文言には要注意。 少しでも違和感を覚えたら、金融庁・国民生活センター・弁護士など信頼できる第三者に相談しましょう。 自分だけで判断せず、家族・友人・専門家の「第三の目」でリスクを最小化することが詐欺防止の第一歩です。
今すぐできる対策としては、SNSのプライバシー設定を見直す・二段階認証を導入する・強いパスワードを使うなどが有効です。また、資産運用では信頼性の高い金融機関の登録業者かどうかを必ず確認しましょう。
安全な投資環境を整えることで、大切な資産を守ることができます!
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!



コメント