米国で続くインフレと金利政策は、日本経済や私たちの生活に大きな影響を与えていますよね? 物価上昇や円安の進行は、日々の生活費だけでなく、株式・不動産・国債といった資産運用にも直結します。つまり、「インフレに強い資産」を理解しなければ、資産価値が目減りしてしまうリスクがあるということです。
実は、アメリカと日本ではインフレの仕組みや中央銀行の対応が異なり、その差が為替や投資環境を大きく左右します。特に2025年以降は、FRBの利上げ動向・日銀の金利政策・地政学リスクが複雑に絡み合うため、投資家や生活者にとって重要な判断材料となります。
この記事では、米国インフレ×日銀政策の行方を基軸に、物価・家計・金融市場への影響と、個人が取れるインフレ対策をわかりやすく整理しました。スマホからでもサッと理解できるように、要点を短く区切って解説していきます。
米国のインフレが日本経済に与える影響(インフレとは・基礎から)

米国で進む**インフレ(物価上昇)**は、日本経済や私たちの生活に少なからず影響を与えています。ドル高・円安の進行や輸入品の値上げを通じて、日本の物価や家計にも波及しているのです。つまり、アメリカのインフレ動向を理解することは、日本で暮らす私たちにとっても欠かせない視点ということですね。
そもそも「インフレ」とは物価が持続的に上がる状態を指し、逆に下がる現象を「デフレ」と呼びます。米国では景気拡大や金融政策の影響でインフレ率が高まり、日本でも輸入コストの上昇などによるコストプッシュ型インフレが進んでいます。
この記事では、まずインフレの基礎知識をわかりやすく解説し、米国と日本それぞれのインフレ率の推移や背景要因を整理していきます。基礎から理解すれば、ニュースや投資判断もよりクリアになりますよ。
1-1. インフレとは?インフレとデフレの違いを簡単に(インフレとは簡単に)
実は「インフレ」とは、物価が持続的に上昇する状態を指します。反対に、物価が下がり続ける現象を「デフレ」と呼びます。
- インフレ(物価上昇):お金の価値が下がるため、同じ金額で買える商品が減る
- デフレ(物価下落):お金の価値が上がるため、消費や投資が冷え込みやすい
つまり、インフレが進むと生活費が高くなりますが、デフレも経済停滞を招くリスクがあるんですね。
ここが重要! インフレは一概に悪いものではなく、経済成長に必要な面もある一方で、急激なインフレは家計に大きな負担を与える点を理解しておきましょう。
1-2. アメリカのインフレ率の現状と推移(アメリカインフレ率・米国インフレ率)
アメリカでは2021年以降、エネルギー高や金融緩和の影響でインフレ率が40年ぶりの高水準に達しました。特に2022年にはCPI(消費者物価指数)が前年比9%近くまで上昇し、FRB(米連邦準備制度理事会)が急速な利上げに踏み切ったのは記憶に新しいところです。
現在は利上げ効果によりインフレ率は落ち着きつつありますが、サービス価格や賃金上昇による粘着的なインフレが課題です。
👉 最新のアメリカCPIデータは 米労働統計局(BLS公式サイト) をチェックすると安心です。
1-3. 日本インフレ率の推移と要因(コストプッシュインフレ/デマンドプルインフレ)
日本では長年デフレ傾向が続いてきましたが、近年は**輸入価格上昇や円安の影響で「コストプッシュ型インフレ」**が進行しています。
- コストプッシュインフレ:輸入エネルギー・原材料費の高騰で物価が押し上げられる
- デマンドプルインフレ:賃金上昇や消費拡大で需要が高まり、物価が上がる
現状の日本は賃金の伸びが追いつかず、家計の負担が増えている状況です。つまり、日本のインフレは「景気が良いから物価が上がっている」というより、外部要因で物価が上がる苦しいインフレという特徴があるのです。
物価上昇の実態と今後(日本インフレ・物価上昇インフレ)

日本の物価上昇は、私たちの生活に直結する大きなテーマですよね。最近はエネルギーや食品価格の上昇が目立ち、「家計の負担が重い」と感じる人が増えているのも事実です。では実際に、どのように物価上昇を測り、今後の見通しを立てればよいのでしょうか。
その基本となるのが「CPI(消費者物価指数)」です。総合CPIは全体の物価を示し、エネルギーや生鮮食品を除いた「コアCPI」は物価の基調を知るために使われます。最近の日本インフレ率を見ると、ガソリン・電気代・食品の寄与度が高く、生活必需品を中心に上昇しているのが特徴です。
この記事では、物価上昇率の見方・生活必需品の価格動向・今後のシナリオの3点を整理します。ディスインフレ(鈍化)なのか再加速なのか、今後の方向性を知ることで、家計防衛や投資判断に役立てられます。
2-1. 物価上昇率の見方:総合CPIとコアCPI、エネルギー・食品の寄与
物価の上昇度合いを測る代表的な指標が**CPI(消費者物価指数)**です。CPIには「総合」と「コア」があります。
- 総合CPI:エネルギー・食品を含む全体の物価動向
- コアCPI:変動が大きいエネルギー・生鮮食品を除き、基調的な物価動向を把握
実は、短期的にはエネルギーや食品の価格が大きく影響します。たとえば原油高や円安でガソリンや電気代が急騰すると、CPI全体を押し上げるのです。
ここが重要! 総合CPIだけでなく、基調を表すコアCPIも併せて確認することで「一時的な上昇か、持続的なインフレか」を判断できる点です。
👉 参考:日本銀行「消費者物価指数(CPI)」最新データhttps://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.html?utm_source=chatgpt.com
2-2. 日本の生活必需品・サービスの価格動向(日本インフレ率 日本 最新)
最近の日本インフレ率では、食品・日用品・公共料金の値上げが続いています。スーパーでの買い物やガス・電気代の請求額を見て「高いな」と感じる方も多いですよね。
- 食品:輸入小麦・食用油の値上げ → パンや麺類に波及
- 光熱費:円安+エネルギー価格高騰で電気代が上昇
- サービス:人件費増加を背景に外食・宿泊費が値上げ
つまり、インフレ率は単なる統計数字ではなく、日々の生活に直接影響しています。特に家計に占める割合の大きい「食品・光熱費」の上昇は家計防衛策を考える上で無視できません。
2-3. 物価見通し:ディスインフレ/再加速の二つのシナリオ
今後の物価はどうなるのでしょうか?大きく2つのシナリオがあります。
- ディスインフレ(鈍化シナリオ)
- 賃金の伸びが限定的
- エネルギー価格の落ち着き
- 景気減速による消費抑制
- 再加速シナリオ
- 円安が進行し輸入コスト増
- 賃上げが広がりサービス価格が上昇
- 地政学リスクによる資源高
つまり、日本の物価は「世界情勢・円相場・国内賃金動向」の3つがカギを握っています。
ここが重要! 短期的には円安や資源価格で変動しやすい一方、中長期的には賃上げが安定すれば持続的インフレへ移行する可能性がある点です。
暮らしへの影響(賃金・家計・消費者行動の変化)

インフレはニュースでよく耳にしますが、実際に気になるのは「私たちの暮らしにどう影響するのか?」という点ですよね。物価が上がっても給料(名目賃金)が同じままだと、実質賃金が下がり、生活水準が目減りすることになります。
さらに、日本特有の円安インフレは輸入品の価格を押し上げ、エネルギー代・食品・家賃にまで波及しています。そのため「日々の買い物が高く感じる」という実感につながりやすいのです。
一方で、インフレには全てが悪い面ばかりではなく、資産を持つ人にとっては「実物資産の価値が上がる」というメリットもあります。こうした変化に応じて、消費行動も「節約志向」と「プレミアム志向」の二極化が進んでいるのが現状です。
この記事では、実質賃金・円安インフレ・消費行動の変化を整理し、暮らしにどう向き合うかを解説します。
3-1. 実質賃金とインフレの関係(インフレ悪い?メリット/デメリット)
実は、インフレ自体には良い面と悪い面があります。
- メリット:企業の売上増 → 賃上げにつながる可能性
- デメリット:物価が賃金上昇を上回ると実質賃金が低下
つまり、給料が増えても物価がそれ以上に上がれば、生活水準は下がってしまうんですね。
ここが重要! インフレの恩恵を受けるには、賃金上昇が物価上昇を上回るかどうかが最大のポイントです。
3-2. 円安インフレで家計はどう変わる?(エネルギー・輸入食品・家賃)
円安が進むと輸入品が高くなり、生活コストに直結します。
- エネルギー:電気・ガス・ガソリン代が上昇
- 食品:小麦・油・肉など輸入比率の高い食材が値上げ
- 住居費:都市部では賃料上昇も
つまり、円安インフレは「給料は変わらないのに支出だけが増える」という厳しい状況を生みやすいのです。
3-3. 消費パターンのシフト:節約行動とプレミアム需要の二極化
興味深いのは、物価上昇の中で消費行動が二極化している点です。
- 節約志向:スーパーの特売やまとめ買い、格安商品の需要が増加
- プレミアム志向:旅行・高級グルメ・ブランド品など「価値あるものにお金を使う」層も増加
つまり、インフレ下では「節約と贅沢が共存する消費行動」が進んでいるんです。
ここが重要! 家計防衛だけでなく、ライフスタイルに合わせたお金の使い方を工夫することが、これからの時代には欠かせません。
金融政策の比較:日銀とFRBの対応(インフレと金利)

インフレ対策の成否を大きく左右するのが、各国の中央銀行による金融政策です。特に、日本銀行(日銀)とアメリカ連邦準備制度理事会(FRB)の対応は、金利や為替、そして日本経済に直接影響を与えます。
日銀は長年の低金利政策やYCC(イールドカーブ・コントロール)を通じて、緩やかなインフレを目指しています。一方でFRBは、急激なインフレ抑制のため積極的な利上げを実施し、世界の金融市場を動かしてきました。
この違いは、円安ドル高の進行や日本の物価上昇につながる大きな要因となっています。つまり、日銀とFRBのスタンス比較は、私たちの生活や投資戦略に直結するテーマなのです。
ここでは、日銀の現状と課題、FRBの判断軸、日本への波及効果、そしてスタグフレーション回避のポイントを解説します。
4-1. 日銀の現状:金利・YCC・インフレターゲット(期待インフレ率)
日銀は長らく**低金利政策とYCC(イールドカーブコントロール)**を維持しています。これは、10年国債の利回りを一定の範囲に抑える仕組みで、企業の資金調達コストを下げ、景気を刺激する狙いがあります。
- 政策金利は依然としてゼロ近辺
- YCCで長期金利の上昇を抑制
- インフレ目標は「2%」だが、達成は一時的要因に依存
つまり、日銀は「持続的な賃上げと安定したインフレ」が確認できるまで慎重に動いていない状況なんです。
ここが重要! 日本は欧米と違い「デフレ脱却」が大前提であり、政策変更は一歩遅れる傾向がある点です。
4-2. FRBの利上げ・据え置きの判断軸と日本への波及(利上げインフレ)
FRB(米連邦準備制度理事会)はインフレを抑えるために積極的な利上げを行ってきました。
- インフレ率が高い → 利上げで景気を冷やす
- 雇用や成長への悪影響が見えれば → 利上げを停止または利下げ
この政策はドル高・円安を生み、日本の輸入物価を押し上げる要因となります。
つまり、アメリカの金利動向は日本の物価や家計に直結しているのです。
ここが重要! 「FRBが利上げをすれば円安・インフレが進む」という構図を理解しておくことが欠かせません。
4-3. 金融政策の効果と限界:スタグフレーション回避の鍵
金融政策は万能ではありません。利上げや利下げで調整できるのは「需要サイド」であり、エネルギー価格や地政学リスクといった供給サイドの問題には限界があるのです。
- 利上げ → 需要抑制には有効
- 供給制約 → 金融政策だけでは解決不可
- 景気後退と物価高が同時に起きれば「スタグフレーション」リスク
つまり、金融政策だけでなく、財政政策や構造改革と組み合わせて対応する必要があります。
ここが重要! スタグフレーションを避けるには「物価安定+成長戦略」が両立する政策が求められるという点です。
インフレが資産に与える影響(インフレに強い資産は何か)
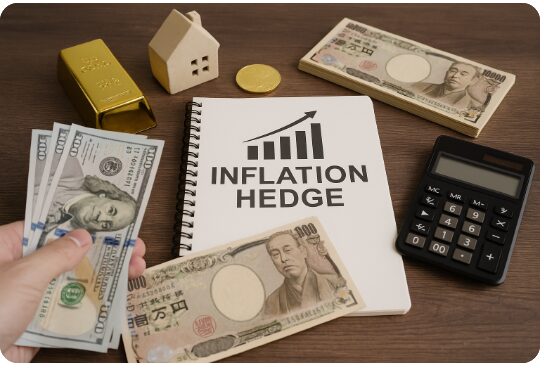
インフレが進むと、もっとも影響を受けるのが私たちの「資産の価値」です。現金のまま保有していると購買力が下がり、知らぬ間に生活コストが上昇してしまいます。そこで重要になるのが、インフレに強い資産への分散投資です。
株式や不動産、金などのコモディティは、インフレ局面で比較的価値を保ちやすいといわれています。また、日本では「物価連動国債」といった金融商品も個人投資家に活用されています。
つまり、インフレ対策では「どの資産をどれくらい持つか」という資産配分がカギになるのです。ここでは、現金のリスク、株式・不動産・コモディティの強み、債券の役割を整理し、個人ができる実践的なインフレ対策を解説します。
5-1. 現金価値の目減りと資産配分の重要性(インフレ対策個人)
インフレ時に最も弱いのが「現金」です。物価が上がると同じ100万円でも買えるモノやサービスは減ってしまいます。
- 預金金利はほぼゼロ → 実質的に資産が目減り
- インフレ率が2%なら、5年で10%以上価値が減少
つまり、現金だけに頼るのは危険です。
ここが重要! インフレ対策には資産を複数に分散し、現金比率を適切に管理することが欠かせません。
5-2. 株式・不動産・コモディティの耐性(インフレに強い株/不動産インフレ)
インフレに比較的強い資産には以下があります。
- 株式:企業が価格転嫁できれば利益増につながる
- 不動産:賃料や物件価格がインフレに連動しやすい
- コモディティ(原油・金):物価上昇と連動しやすく「インフレヘッジ」として有効
実は、全ての株がインフレに強いわけではありません。特に資源・インフラ・生活必需品セクターは価格転嫁力が強く、インフレ環境でも安定しやすいです。
ここが重要! 「どの銘柄や資産クラスがインフレに強いか」を見極めることが資産防衛のカギになります。
5-3. 債券・国債・物価連動債の位置づけ(インフレ国債/ブレークイーブンインフレ率)
債券は通常インフレに弱い資産ですが、例外もあります。
- 通常の国債・社債:固定利回りのためインフレに弱い
- 物価連動国債:インフレ率に応じて元本や利払いが増える仕組み
- ブレークイーブンインフレ率:市場が予測する将来のインフレ率を示す指標
つまり、インフレ局面では「通常の債券」ではなく「物価連動債」を組み込むことが有効なんです。
ここが重要! 債券でも工夫すればインフレ対策の一部になり得るという点です。
2025年以降のインフレ予測(世界インフレ率と日本の中長期)

2025年以降のインフレ動向は、世界経済と日本経済の行方を左右する大きなテーマです。米国では利上げや金融政策の転換により「ディスインフレ(物価上昇の鈍化)」が進む可能性がある一方、資源価格や地政学リスク次第では再びインフレが加速するシナリオも想定されています。
日本においては、賃金上昇・生産性改善・円相場の動きがインフレ率を左右する重要な要因です。とくに円安が続けば輸入コスト増による物価高が続き、家計に直結する影響を及ぼします。
また、原油価格や供給網の制約、さらには地政学リスクがインフレを押し上げる要因になる可能性もあります。**「ハイパーインフレの誤解」**も整理しつつ、現実的なリスクと予測を理解することが、これからの資産防衛には欠かせません。
6-1. 世界インフレ率・米国インフレのシナリオ(ディスインフレ/再インフレ)
世界経済は「ディスインフレ」と「再インフレ」のどちらにも進む可能性があります。
- ディスインフレシナリオ:利上げ効果で需要が減退し、物価上昇が落ち着く
- 再インフレシナリオ:原油高や供給網の混乱で再び物価が上昇
つまり、米国の金融政策と国際情勢が今後の物価に大きく影響するのです。
ここが重要! 世界インフレ率は「エネルギー価格」と「金融政策次第」で方向性が変わるという点です。
6-2. 日本インフレ率見通し:賃金・生産性・円相場の三要因
日本のインフレ率を左右するのは主に3つの要因です。
- 賃金:賃上げが物価上昇と連動すれば持続的なインフレが定着
- 生産性:生産性向上がなければコスト増だけが続く
- 円相場:円安が続けば輸入物価の上昇でインフレが加速
つまり、賃金と生産性の両立がなければ「悪いインフレ」になりかねないのです。
ここが重要! 日本の持続的インフレは「賃金上昇+生産性改善+円相場安定」の三位一体で実現します。
6-3. リスク要因:地政学・供給制約・原油価格・ハイパーインフレの誤解
インフレ見通しにはリスクも多く存在します。
- 地政学リスク:中東や東アジアでの緊張が原油価格を押し上げる
- 供給制約:半導体やエネルギーの供給不足が価格上昇を加速
- 原油価格:上昇すれば即座に輸送・製造コストに波及
- ハイパーインフレの誤解:日本の現状は「急激な物価崩壊」ではなく、緩やかな上昇が中心
ここが重要! リスク要因を冷静に把握し、過度に悲観するのではなく「現実的なインフレ対策」を取ることが大切です。
金融市場への波及(株・為替・債券)

インフレや金利の動きは、株式・為替・債券といった金融市場に直結する重要なテーマです。たとえば金利が上昇すると、株式市場ではグロース株よりもエネルギーや金融などの「インフレ耐性セクター」が注目されます。一方、輸出企業に有利な円安が進めば、為替市場でもドル高・円安の流れが鮮明になり、家計や投資に影響を与えます。
さらに、債券市場では利回り曲線の変化が投資家心理に大きなシグナルを与えます。長らく続いた低金利環境からの「正常化」は、資産運用やリスク管理の見直しを迫るものです。
つまり、インフレ局面では各市場の動きを理解し、どの資産が恩恵を受け、どこにリスクがあるのかを冷静に見極めることが成功へのカギとなります。
7-1. 株式市場:金利上昇時のセクター選別と「インフレ銘柄」
金利上昇は株式市場に逆風となることが多いですが、全ての銘柄が下がるわけではありません。
- 不利なセクター:ハイテク株や成長株(資金調達コスト増で利益圧迫)
- 有利なセクター:エネルギー・素材・金融(価格転嫁や金利上昇メリット)
- インフレ銘柄:食品や生活必需品など価格転嫁力のある企業
ここが重要! 金利上昇局面では「セクターを選ぶ投資戦略」が欠かせません。
7-2. 為替市場:金利差とドル高・円安のメカニズム(円安インフレ)
為替市場は金利差で動く傾向が強く、米国が利上げ、日本が低金利を維持するとドル高・円安が進みます。
- ドル高 → 輸入コスト増で日本の物価上昇要因
- 円安 → 輸出企業にはプラス、家計にはマイナス
つまり、為替市場の動きは「企業と家計で真逆の影響」が出るのです。
ここが重要! 為替の円安進行は日本経済に二面性を持つため、投資や家計防衛では要注意です。
7-3. 債券市場:利回り曲線・久しぶりの金利正常化が意味するもの
長らく続いた低金利からの「金利正常化」は債券市場に大きな変化をもたらしています。
- 利回り曲線の変化:長期金利が上昇し、債券価格が下落
- 投資家の選択肢:株や不動産だけでなく債券も再び有力な資産に
- 物価連動債の注目:インフレ局面ではリスクヘッジとして価値が高まる
ここが重要! 債券市場の正常化は「分散投資の再評価」を促しているという点です。
個人ができるインフレ対策(家計・投資・保険)

インフレが続くと、日々の生活費や資産運用への影響が気になりますよね。実は、個人でも今からできるインフレ対策は数多くあるんです。家計の見直し、投資の分散、そして保険や税制の活用まで、ポイントを押さえれば将来の不安をぐっと減らせます。
例えば家計編では、固定費の削減や値上げへの工夫が効果的。投資編では、株式・不動産・コモディティをバランスよく組み合わせることで、インフレに強いポートフォリオを築けます。さらにリスク管理として、長期積立やリバランス、NISA・iDeCoなどの税制優遇制度を組み合わせれば、資産形成の効率も高まります。
つまり、日常の工夫と投資戦略を両立させることがインフレ時代の最適解なんですね。
8-1. 家計編:固定費圧縮・価格転嫁への対応・ポイント活用
インフレ時は「固定費の見直し」が最も即効性のある対策です。
- 通信費・保険料の削減:格安プランや見直しで数千円節約可能
- 光熱費対策:節電・省エネ家電への切替で支出を抑制
- 価格転嫁への対応:値上げされた商品は「代替品」や「まとめ買い」で対策
- ポイント・キャッシュレス活用:PayPay、楽天ポイントなどで家計防衛
ここが重要! 家計のインフレ対策は「固定費の削減+賢い消費行動」で生活防衛を強化することです。
8-2. 投資編:インフレ耐性のあるポートフォリオ構築(比率と分散)
投資では「インフレに強い資産」を組み込むことが欠かせません。
- 株式:価格転嫁できる企業(食品・エネルギー・生活必需品)
- 不動産:賃料上昇が期待できる収益物件やREIT
- コモディティ:金・原油などインフレ局面で強い資産
- 分散投資:地域・通貨・資産クラスを組み合わせてリスク分散
ここが重要! インフレ局面では「株・不動産・コモディティ」を組み合わせ、長期的に安定するポートフォリオを構築するのが効果的です。
8-3. リスク管理:長期積立/リバランス/税制優遇の活用
投資はインフレ対策になりますが、リスク管理も忘れてはいけません。
- 長期積立:ドルコスト平均法で価格変動リスクを抑制
- リバランス:定期的に資産配分を調整し、偏りを防ぐ
- 税制優遇:NISAやiDeCoを活用し、税負担を減らして資産を効率的に増やす
ここが重要! リスク管理は「積立・分散・税制活用」の3本柱で、インフレ環境でも安定した資産形成を実現できます。
国際比較と学び(米国・欧州・新興国のケース)

インフレは世界共通の課題ですが、各国の対応策や経済環境によって結果は大きく異なるのをご存じですか?アメリカや欧州では金利政策を通じた抑制策が進む一方で、トルコやアルゼンチンのように高インフレに直面する国々は、通貨価値の下落や急激な物価上昇に苦しんでいます。
日本にとっても、輸入物価や供給網の弱さは無視できないリスクです。しかし同時に、生産性向上や新しい産業育成を進めることで、経済を強化するチャンスでもあります。
つまり、国際比較から学べるのは「短期対応」と「長期戦略」を両立させる重要性です。賃上げ・為替・構造改革を組み合わせた一体的なアプローチこそが、日本経済の安定と成長の鍵になるのです。
9-1. 各国のインフレ動向と政策対応(米国インフレ率・欧州・トルコ・アルゼンチン)
- 米国:FRBの積極的な利上げでインフレを抑制
- 欧州:エネルギー価格高騰の影響を受けやすく、ECBも利上げで対応
- トルコ・アルゼンチン:通貨安・財政赤字が背景にあり、深刻な高インフレ状態
ここが重要! インフレ抑制には「金融政策+財政健全化」が両立していなければ効果が限定的です。
9-2. 輸入物価と供給網:日本の構造的弱みとチャンス
日本はエネルギー・食料を輸入に依存しているため、円安や供給網の混乱に弱い構造を持っています。
- 弱み:輸入価格上昇で家計や企業コストに直撃
- チャンス:サプライチェーン多様化や再生可能エネルギー開発で改善可能
ここが重要! 日本は「輸入依存からの脱却」と「内需強化」でインフレ耐性を高める必要があります。
9-3. 日本が取るべき長期戦略:生産性・賃上げ・為替の三位一体
長期的に持続可能な成長を目指すなら、以下の3つが不可欠です。
- 生産性向上:デジタル化・AI活用で効率を高める
- 賃上げ:企業収益を従業員に還元し、消費を支える
- 為替安定:過度な円安・円高を防ぎ、安定した輸入価格を確保
ここが重要! 日本のインフレ戦略は「生産性+賃上げ+為替安定」の三本柱で、中長期的な安定成長を実現することです。
結論
今回の記事では、米国のインフレ動向と日銀政策、日本経済への影響、そして個人が取るべきインフレ対策について解説しました。世界的に物価上昇が続く中で、インフレは資産価値や家計に直結する大きなテーマです。
インフレに対処するためには、まず**「現金だけで資産を保有するリスク」**を理解することが重要です。その上で、株式や不動産、コモディティ、さらにはインフレ連動国債など、インフレに強い資産へ分散投資する戦略が求められます。また、固定費の見直しや家計管理アプリの活用など、生活コストを抑える工夫も同時に取り入れるべきです。
さらに、日本と海外の事例を比較すると、賃上げ・生産性向上・為替政策が長期的な安定の鍵であることが見えてきます。つまり、個人としても「投資」「家計管理」「リスク分散」を組み合わせることで、インフレ時代を乗り切れるということです。
**今日からできる行動は、①家計の固定費を削減、②少額からでも分散投資を開始、③ニュースや公式データで最新のインフレ動向を確認すること。**この3つを意識すれば、将来の不安を大きく減らすことができます。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!



コメント