退職金が2,000万円・3,000万円になると、「税金でどれくらい引かれるの?」と不安になりますよね。
実は、退職金の受け取り方や準備のタイミングで、税金は大きく変わるんです。
特に、退職金には「退職所得控除」という強力な優遇があるため、正しく対策すれば手取り額を最大化できます。
逆に、対策をしないまま退職してしまうと、所得税・住民税・社会保険などで損をしてしまうケースも多いんです。
そこで本記事では、
・退職金の税金の仕組み
・年収別・退職金別の税金シミュレーション
・ふるさと納税・NISA・iDeCoの使い方
・退職後の所得税・住民税の注意点
などを、初心者向けにやさしく・シンプルに解説します。
つまり、この記事を読むことで、退職金を1円でも多く残すために今日からできる対策がすべてわかるということですね!
退職金の税金対策とは?サラリーマン・公務員が最初に知るべき基本

退職金を受け取る前に、まず知っておきたいのが「退職金の税金がどう決まるのか」という基本ですよね。
実は、退職金には他の収入とはまったく違う特別な税金計算ルール(退職所得控除)があり、これを理解しているかどうかで手取りが100万円以上変わることも珍しくありません。
サラリーマンや公務員の方は、会社(役所)が自動で税金を計算してくれるため、「自分では対策できない」と思いがちですが、実は退職前の準備次第で節税効果を大きく伸ばすことができます。
さらに、年収700万〜1000万円の方は、退職後に住民税・健康保険料・所得税が増える可能性があるため、事前の対策が必須レベルになります。
この章では、退職金の基礎・税金の仕組み・サラリーマンが最初にやるべき対策をわかりやすく解説します。
1-1. 退職金の税金対策とは?簡単にわかる「退職所得」と税金の仕組み
実は、退職金の税金はふつうの給料とはまったく違う仕組みになっています。
その理由は「退職所得」という特別枠で課税されるからです。
ポイントは3つです。
📌 退職所得の基本
- 退職金は「退職所得」という別枠で税金計算される
- 勤続年数が長いほど税金は安くなる
- **退職所得控除」という超強力な控除が使える
- 課税されるのは「(退職金 − 退職所得控除)÷2」の半分だけ**
つまり、同じ2,000万円でも 勤続年数によって税金がほぼゼロになることもあるということですね。
ここが重要!
→ 退職金は「控除」「勤続年数」「受け取り方」で税金がまったく変わります。
1-2. サラリーマン・公務員の退職金にかかる所得税・住民税と税金対策サラリーマンの基本
サラリーマンや公務員の場合、税金の計算は会社・役所が自動でやってくれます。
しかし、自動計算だからこそ 自分で対策しないと損しやすいんです。
📌 税金の基本
- 所得税 → 退職時に一括計算されて源泉徴収
- 住民税 → 原則、翌年の税額に反映される
- 社会保険 → 任意継続や国保に切り替えるタイミングで大きく変動
特に住民税は「前年の所得」で決まるため、退職後に 急に住民税が高くなることがあります。
📌 最初にやるべき税金対策
- 退職金の受け取り方を確認する
- 退職年度の所得調整(副業停止・売却益の調整など)
- 退職前にふるさと納税の上限をチェック
- 社会保険の選択(任意継続 or 国保)
つまり、退職金だけではなく「退職後の税金」まで見ておかないと損しやすいということですね。
1-3. 年収700万・900万・1000万の人が退職金税金対策を急ぐべき理由
実は、年収700万〜1000万ゾーンの人が 退職金で最も損しやすい層 なんです。
理由はシンプルで、この年収帯は「住民税・健康保険料・所得税」が重くなりやすいから。
📌 この年収帯の人が注意すべきポイント
- 税率が高いため、退職金に影響しやすい
- 退職後の住民税がグッと重くのしかかる
- 任意継続の保険料が高額になるケースが多い
- 再就職・副業で所得が増えると課税が複雑化
さらに、退職金が2,000万〜3,000万円以上あると、
少しの判断ミスで税金が100万円単位で変わる可能性があります。
📌 今日からできる対策
- 退職金の「控除額」を早めに確認
- ふるさと納税の上限を把握
- 年末調整・確定申告の影響を理解
- 退職後の働き方(副業・再雇用)を早めに決める
ここが重要!
→ 年収700万〜1000万の人ほど「退職前の準備」で税金対策の効果が大きくなります。
退職金の税金はいくら?退職所得控除と計算方法を徹底解説
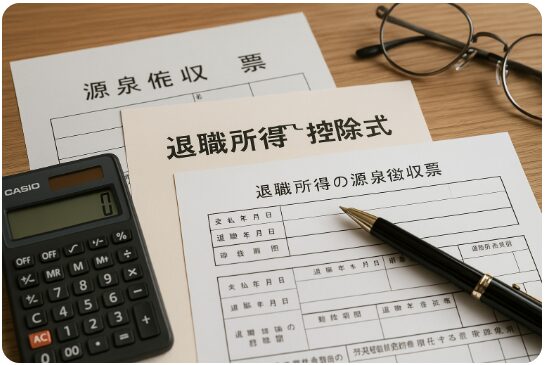
退職金の税金はいくらになるのか、具体的な数字を知りたいですよね?
実は、退職金の税額は 「退職所得控除」+「特別な計算式」 の2つで決まり、他の所得とは全く違う優遇が受けられます。
この退職所得控除は、勤続年数が長いほど控除額も増える仕組みで、場合によっては退職金がほぼ非課税になるケースもあります。
ただし、勤続20年を境に控除額が大きく変わるため、計算方法を理解しておくことがとても大切です。
さらに、税額を正しく把握するには、
・源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・勤続年数の確認
といった資料が必須になります。
この章では、退職所得控除の計算式、勤続年数別の早見表、そして年収別の具体的な計算例まで、初心者にもわかりやすく徹底解説します。
2-1. 退職所得控除の計算式と早見表|勤続年数別の退職金税金対策の考え方
退職所得控除とは、退職金から差し引ける「非課税枠」のことです。
実はこれが非常に強力で、多くの人が 退職金にほとんど税金がかからない理由になっています。
📌 計算式(誰でも同じ)
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数−20年)
つまり、勤続30年の場合は以下のようになります。
800万円+70万円×10年=1,500万円 が非課税になります。
勤続35年なら
800万円+70万円×15年=1,850万円
ここが重要!
→ 勤続年数が長いほど控除が増え、税金はほぼゼロに近づきます。
2-2. 源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票など税金計算に必要な情報と確認ポイント
退職金の税額を正しく知るためには、以下の書類が必要です。
📌 必要書類
- 退職所得の源泉徴収票(必須)
- 源泉徴収票(給与分)
- 勤続年数がわかる書類(辞令・雇用契約など)
- 退職金規程(企業によって計算方法が異なる)
📌 ここは必ず確認
- 支給額(税引前)
- 退職理由(会社都合・自己都合で控除が変わる場合あり)
- 勤続年数
- 源泉徴収されている税額
退職所得の源泉徴収票は 確定申告のときに必ず必要なので、絶対に捨てないようにしてください。
2-3. 【具体例】年収500万・年収900万の場合の退職金の税金計算シミュレーション
実際の数字を見ると、退職金の税金がどれだけ優遇されているかがよくわかります。
📌 年収500万円・勤続30年・退職金1500万円の場合
- 控除:1,500万円
- 課税対象:0円
→ 税金はゼロ!
📌 年収900万円・勤続28年・退職金2000万円の場合
- 控除:800万円+70万円×8年=1,360万円
- 課税対象: (2,000万円 − 1,360万円) ÷ 2=320万円
- 税金:所得税&住民税合わせても 約20〜30万円
つまり
高年収でも退職金は圧倒的に優遇されており、税金はかなり安いということですね。
退職金の税金を減らす節税対策|ふるさと納税・iDeCo・NISAの使い方
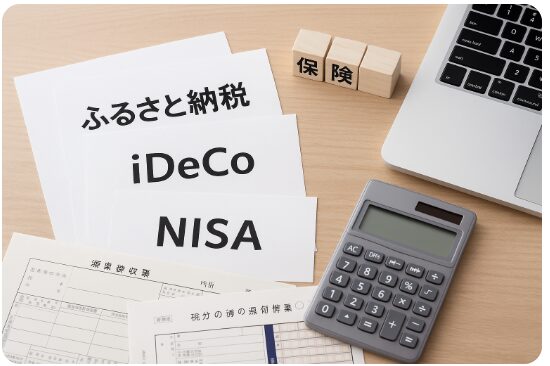
退職金の手取りを1円でも多く残したいなら、「退職前後にできる節税対策」を知っておくことがとても重要です。
実は、ふるさと納税・iDeCo・NISA・保険などは、退職金と組み合わせることで節税効果が一気に大きくなるタイミングがあるんです。
特に、ふるさと納税は退職年の年収が下がる前に活用するのがコツで、iDeCoは掛金が全額所得控除になるため、税金を大幅に減らすことができます。
さらに、個人年金・学資保険・生命保険などは、受け取り方を工夫することで課税を抑えながら家計の負担を軽くすることが可能です。
ただし、どれも「タイミングを間違えると逆に損をする」ことがあるため、退職前後の流れをしっかり理解しておく必要があります。
この章では、ふるさと納税・iDeCo・NISA・保険の使い方を、退職金と組み合わせた最適な節税戦略としてわかりやすく解説します。
3-1. 退職前後にできるふるさと納税税金対策|控除上限とタイミングのコツ
ふるさと納税は「退職年」が最も効果が大きくなる制度です。
理由はシンプルで、退職前のほうが年収が高く、控除上限が大きいからです。
📌 タイミングのコツ
- 退職年の“1月〜退職月”までの年収で控除上限が決まる
- 退職後は年収が下がるため、控除上限も大幅に減る
📌 やるべきこと
- 退職前に控除上限額をチェック
- 楽天ふるさと納税・ふるさとチョイスなどで上限シミュレーション
- 年末ギリギリに駆け込みで寄付してもOK
ここが重要!
→ 退職前にふるさと納税をやるだけで、数万円の節税効果があります。
3-2. iDeCo・NISA・積立NISA税金対策|退職金と組み合わせるメリット・デメリット
iDeCo・NISAは退職金との相性がとても良いです。
理由は「税金ゼロで資産を増やせる期間を長くできる」から。
📌 iDeCoのメリット
- 掛金が全額所得控除
- 運用益も非課税
- 受け取り時に退職所得控除・公的年金控除が使える
📌 NISAのメリット
- 運用益が完全非課税
- 退職金を投資に回す受け皿として便利
📌 注意点
- iDeCoは60歳まで引き出せない
- リスク資産は元本割れの可能性あり
つまり、
長期運用を前提にするならiDeCo、柔軟に使いたいならNISAが向いています。
3-3. 個人年金・学資保険・生命保険税金対策としての活用ポイント
保険は「節税+将来のお金作り」の両方を兼ねられる便利な手段です。
📌 活用方法
- 個人年金保険:受け取り時に雑所得だが、節税しながら積み立て可能
- 生命保険:相続対策として特に有効
- 学資保険:教育資金目的で効率的に積み立てできる
📌 こんな人におすすめ
- 安定した貯蓄を作りたい
- 相続税を減らしたい
- 退職金の一部を安全資産に回したい
ここが重要!
→ 保険は「節税目的」よりも「資産目的・相続目的」で使うと効果が大きいです。
退職後の税金対策|年金・副業・フリーランス・個人事業主のポイント

退職後は「年金・副業・フリーランス・個人事業主」など、働き方が大きく変わるタイミングですよね。
実は、この働き方の変化によって 税金の仕組みもガラッと変わるため、対策を知っているかどうかで手取りが大きく変わります。
まず、公的年金・個人年金には 年金控除 という優遇があり、税金がかなり軽くなる仕組みがあります。
一方で、副業やフリーランスとして働く場合は、経費を上手く使うことで課税所得をグッと抑えることができます。
さらに、退職後は年収が下がるタイミングがあるため、住民税・健康保険料が急に高く感じるケースも多いんです。
つまり、退職後ほど「税金の見直し」が必要になるということですね!
この章では、年金の税金の基本、副業・フリーランスの節税ポイント、そして退職後に必ず確認したい税金チェックリストまで、初心者にもわかりやすく解説します。
4-1. 公的年金・個人年金の税金対策|年金控除と年金の税金対策の基本
退職後の収入の中心となるのが「公的年金」です。
実は年金には 年金控除 という強力な優遇があり、税金が驚くほど安くなります。
📌 公的年金の税金の仕組み
- 年金収入から「公的年金控除」を差し引く
- 残った金額が課税対象
- 65歳以上は控除額が大きくなる
たとえば、65歳以上なら
年金年収の110万円まで非課税(単身の場合) になります。
📌 個人年金の扱い
- 個人年金は「雑所得」扱い
- 公的年金と合算されるため、年金受け取りの総額に注意
- 受け取り方を年金型・一時金型で分けることで節税ができる
ここが重要!
→ 年金は「控除が大きい」「受け取り方で節税できる」という2つを押さえるだけでOK。
4-2. 副業・フリーランス・業務委託・一人親方の経費を使った個人事業主税金対策
退職後は副業やフリーランスを選ぶ人が増えています。
なぜかというと、経費が使えるため課税所得を自由に調整できるからです。
📌 使える経費の例
- スマホ代
- 自宅家賃の一部(家事按分)
- パソコン、機材、通信費
- 交通費
- 仕事に関係する書籍、研修費
経費を使うと
売上 − 経費 = 課税所得
となり、税金を大きく抑えることができます。
📌 個人事業主のメリット
- 経費が自由に使える
- 青色申告で最大65万円控除
- 国民健康保険より「国保+扶養」のほうが有利なケースもあり
つまり、副業を始めるだけで“税金を上手にコントロールできる”ようになるわけです。
4-3. 退職後税金対策チェックリスト|年収・世帯年収別の所得税・住民税の注意点
退職後は年収が変動するため、税金も大きく変わります。
特に「前年の所得」で決まる住民税は注意が必要です。
📌 チェックすべきポイント
- 退職翌年の住民税が高くなる
- 再就職・副業で年収が増えると税率が上がる
- 国保が高額になるケースもある
- 扶養に入れるかどうかで控除額が変わる
📌 年収別で注意すべき人
- 年収300万円付近 → 住民税が減りやすい
- 年収500万円付近 → 医療費控除・保険料の影響が大きい
- 年収700万円以上 → 税率が急上昇するライン
ここが重要!
→ 退職後は「翌年の住民税」と「社会保険」の2つを必ずチェックしましょう。
退職金と相続・贈与の税金対策|不動産・現金・保険の組み立て方
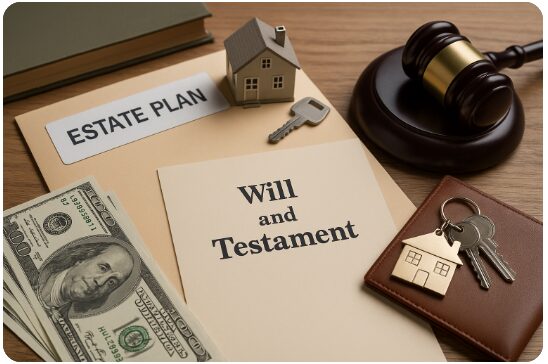
退職金は「老後資金」というだけでなく、実は 相続税・贈与税の節税戦略としても非常に重要な役割を持っています。
つまり、退職金の扱い方によって、家族が受け取る遺産の税金が大きく変わる可能性があるということですね!
特に、退職金はみなし相続財産として扱われるケースがあるため、相続税の計算に影響することがあります。
また、生前贈与を活用すれば、子どもや配偶者に資産を移しつつ、贈与税を抑える方法もあります。
さらに、不動産・土地・生命保険などを組み合わせることで、相続税の負担を大幅に軽くできるケースも多く、退職金と合わせた資産設計がとても重要になります。
この章では、退職金が相続税にどう影響するのか、贈与に使えるか、不動産や保険と組み合わせる最適な方法などを、初心者にもわかりやすく解説します。
5-1. 退職金が相続税・遺産相続税金対策に与える影響と基礎知識
退職金には「みなし相続財産」として扱われるケースがあります。
これは死亡退職金の場合で、相続税の対象です。
📌 相続税の計算ポイント
- 死亡退職金は相続税の対象
- ただし非課税枠あり
- 500万円 × 法定相続人の数 が非課税枠
📌 退職金が影響する場面
- 自分の資産総額が増える
- 相続税の課税ライン(3,600万円)が変動
- 不動産・保険と合わせて税額が大きく変わる
ここが重要!
→ 退職金があるだけで「相続税の対象になる可能性」が高まります。
5-2. 生前贈与・贈与税と退職金の関係|子ども・配偶者への贈与税金対策のポイント
退職金を一部贈与しておくことで、相続税を大きく抑えられます。
📌 贈与税の基本
- 年110万円まで非課税(暦年贈与)
- 配偶者控除で最大2,000万円まで非課税(不動産)
📌 退職金と贈与の組み合わせ
- 退職金の一部を非課税枠の範囲で贈与
- 毎年110万円ずつ移すと資産圧縮効果が大きい
- 子どもが未成年・学生の場合は教育資金贈与も使える
つまり、退職金を“計画的に贈与”するだけで相続税が大きく下がります。
5-3. 不動産相続・土地相続・生命保険を組み合わせた不動産税金対策・相続税金対策
相続税は「不動産」と「生命保険」の組み合わせで大きく節税できます。
📌 不動産の節税効果
- 評価額が現金の6〜7割に下がる
- 賃貸物件はさらに評価が減りやすい
- 土地を分筆すると相続税が下がることも
📌 生命保険の節税効果
- 受取額が非課税枠の対象
- 相続対策として最も使いやすい商品
- 現金としてすぐ使えるためトラブルを防ぐ
📌 最適な組み合わせ
- 退職金 → 現金
- 不動産 → 評価額圧縮
- 生命保険 → 非課税枠の活用
ここが重要!
→ 現金だけで相続すると損。
→ 不動産・保険と組み合わせると節税効果が最大化します。
税理士・FPに相談して退職金税金対策を最適化する方法

退職金の税金対策は、自分で調べても複雑で「本当にこれで合っているのかな…?」と不安になりますよね。
実は、退職金・相続・法人化の税金は専門知識が必要なため、税理士やFPに相談するだけで、手取りが大きく増えるケースが珍しくありません。
特に、退職金は金額が大きいので、ちょっとしたアドバイスで 数十万円〜数百万円の節税効果 が出ることもあります。
さらに、オンライン相談や無料相談を利用すれば、費用を抑えながら最適な専門家を見つけることができます。
相談時には「準備する書類」や「質問すべき項目」を知っておくことで、ムダなく、より正確なアドバイスを受けられます。
つまり、専門家を上手に活用することが、退職金の手取りを最大化する近道ということですね!
この章では、税理士・FPの選び方、相談のコツ、依頼する際の注意点までわかりやすく解説します。
6-1. 退職金・相続・法人化に強い税理士法人・FPの選び方と税金対策相談のコツ
税理士やFPはどこに相談しても同じ…ではありません。
実は、専門分野によって 結果が大きく変わるんです。
📌 税理士・FPの選び方
- 退職金・相続・法人化の実績が多い専門家を選ぶ
- 説明がやさしく、初心者にも丁寧
- オンライン相談に対応している
- 資産形成(NISA・iDeCo)の知識がある
- 法人化の手続きをサポートできる事務所だとベスト
📌 相談のコツ
- 事前に収入・退職金・資産状況をまとめる
- 相談したい内容を3つに絞る(退職金・相続・法人化など)
- 現状の問題点や希望も伝える
ここが重要!
→ 専門分野が「退職金・相続・法人化」の税理士を選ぶだけで失敗リスクが激減します。
6-2. 無料相談・オンライン相談を活用した税理士への依頼方法と準備する書類
最近は税理士にも 無料相談 や オンライン相談 が増えています。
費用を抑えつつ、複数の専門家を比較できるのでとても便利です。
📌 無料相談の活用法
- 初回30〜60分は無料の事務所が多い
- 2〜3社は比較するのがベスト
- 専門分野や料金体系を確認する
📌 相談前に準備する書類
- 源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 年金定期便
- 退職金規程
- 資産一覧(銀行・証券・保険)
- 将来の働き方(再就職・副業など)
書類を揃えるだけで、アドバイスの精度が一気に上がります。
6-3. 税理士に依頼して節税効果を最大化するためのポイントと注意点
税理士を使えば節税効果は大きくなりますが、
どんな依頼をするかで結果が大きく変わります。
📌 節税効果を上げるポイント
- 退職金の受け取り方(分割・一括)
- iDeCo・NISA・保険の使い方
- 相続税の事前対策
- 法人化による節税
- 副業・フリーランスの経費計上
📌 注意点
- 料金が高すぎる事務所は避ける
- 法人化を勧めすぎる税理士には注意
- 提案内容が抽象的な税理士も危険
ここが重要!
→ 良い税理士は「受け取り方・相続・法人化」まで一気通貫で提案してくれます。
法人化・会社設立による退職後・役員報酬の税金対策

退職後の働き方として、「法人化して役員報酬を受け取る」という選択肢が人気になっています。
実は、法人をつくることで 税金・社会保険・経費の使い方などが大きく変わり、節税の幅が一気に広がるんです。
特に、一般社団法人・合同会社・株式会社は目的によって節税効果が変わるため、どの形を選ぶかがとても重要になります。
また、社宅制度・福利厚生・生命保険・役員報酬の調整などを組み合わせることで、個人よりも有利な税金設計が可能になります。
さらに、会社売却・ストックオプション・持株会など、経営者ならではの資産形成手段も選べるようになり、将来の資産づくりにも大きなメリットがあります。
つまり、「法人化」は退職後の税金対策としてとても効果的な選択肢ということですね。
この章では、法人化の基礎、役員報酬の決め方、経営者向けの税金戦略までわかりやすく解説します。
7-1. 一般社団法人・合同会社・株式会社を使った法人化税金対策・会社設立 税金対策の基本
法人化の形によって、節税できるポイントが変わります。
📌 各法人の特徴
● 株式会社
- 社会的信用が高い
- 節税の選択肢が多い
● 合同会社(LLC)
- 設立費用が安い
- 小規模事業向け
- 税務がシンプルで使いやすい
● 一般社団法人
- 非営利だが事業はできる
- 相続対策で活用されることも多い
📌 法人化のメリット
- 経費が使える
- 家族を従業員にできる
- 社宅を使える
- 生命保険で節税できる
- 役員報酬で所得を分散できる
つまり、退職後の働き方として法人は“最強クラスの節税手段”です。
7-2. 役員報酬・社宅・福利厚生・保険を活用した法人税金対策・中小企業税金対策
法人化の魅力は「使える節税の種類の多さ」にあります。
📌 法人で使える節税
- 役員報酬の調整(所得分散)
- 社宅制度(家賃の大幅節税)
- 会社負担の保険料
- 経費として計上できる支出
- 福利厚生費の活用
- 車両費・通信費・出張費
たとえば、社宅を使うだけで家賃の6〜8割を会社負担にできます。
ここが重要!
→ 個人では節税できない支出が、法人なら経費になる場合が非常に多いです。
7-3. 会社売却・ストックオプション・持株会を視野に入れた経営者税金対策の考え方
実は、退職後に起業した会社は「売却」も選択肢になります。
会社を売却すると 売却益が譲渡所得となり、税率が下がるため、資産形成として非常に有利です。
📌 経営者が使える資産戦略
- 持株会で株式を保有
- ストックオプションを発行
- 会社を数年後に売却
- 事業を子どもに承継
- 法人名義で不動産を保有
📌 こんな人におすすめ
- 退職後に新しく事業を始めたい
- 税金を抑えつつ収入を増やしたい
- 子どもの代まで資産を残したい
- 最終的に法人を売って現金化したい
つまり、法人化は「節税」だけでなく将来の資産戦略としても非常に強力なんです。
退職金の受け取り方で変わる税金|一括・分割・企業年金・個人年金
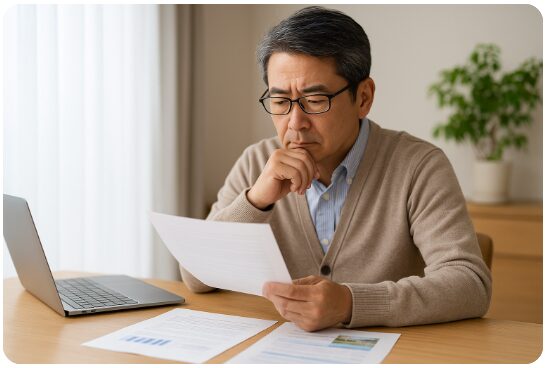
退職金は「どう受け取るか」で税金が大きく変わるのをご存じですか?
実は、一括受取・分割受取・企業年金・個人年金など、受け取り方法によって税金の計算式も手取り額もまったく違うんです。
たとえば、一括受取は退職所得控除が最大限に使えるため、節税効果が最も大きい方法です。
一方で、分割受取や年金受取の場合は、雑所得として毎年課税されるため、年金や副業収入と合算されて税金が増える可能性もあります。
さらに、企業型DCや確定拠出年金、個人年金の受け取り方を組み合わせることで、老後の収入バランスを調整しながら節税につなげることも可能です。
ただし、再雇用・再就職・副業などがある人は、税金の仕組みが複雑になりやすいため、専門家に相談したほうが安心です。
この章では、受け取り方法ごとの税金の違いと、どの選択肢が有利になるのかをわかりやすく解説します。
8-1. 一括受取・分割受取・年金受取の税金比較|どの受け取り方法が有利か?
退職金の受け取り方法は大きく3つあります。
それぞれ税金が全く違うため、最適な選択を知っておくことが大事です。
📌 一括受取(最も節税効果が高い)
- 退職所得控除が最大限使える
- 課税対象は (退職金 − 控除額)÷2
- 税金が最も安くなるケースが多い
→ 高額退職金の人に特に有利!
📌 分割受取
- 年金のように毎年受け取る
- 「雑所得」扱い
- 公的年金や副業収入と合算され、税金が高くなりやすい
→ 年間の収入を抑えたい人に向く
📌 年金受取(個人年金扱い)
- 雑所得として毎年課税
- 公的年金控除の対象にならない
→ 他の年金と合算されるため注意が必要
ここが重要!
→ 一括受取は税金が最も少なくなりやすく、多くの人に有利です。
8-2. 企業型DC・確定拠出年金・個人年金保険を使った退職後の税金対策
退職金と組み合わせて使える制度として、DC(確定拠出年金)や個人年金があります。
これらは受け取り方で税金が変わるため、理解しておくと節税につながります。
📌 企業型DC・iDeCoのポイント
- 一時金受取 → 退職所得控除が使える
- 年金方式 → 公的年金控除が使える
- 受け取り方で節税額が大きく変わる
📌 個人年金保険のポイント
- 雑所得扱い
- 利息部分だけ課税される
- 年金として受け取ると課税所得が増えやすい
📌 組み合わせのコツ
- 高年収の人 → 一時金受取が有利
- 年金収入が少ない人 → 年金方式が有利
- 複数の制度を持っている場合 → 受け取り時期をズラして節税
つまり、
退職金+DC+年金を総合的に設計することで税金を最小化できます。
8-3. 税理士に相談すべきケース|退職金が高額・再雇用・再就職・副業がある場合
退職金の受け取り方は個人によって最適解が違います。
特に以下に該当する人は、税理士に相談したほうが確実です。
📌 税理士に相談すべき人
- 退職金が 2,000万円〜3,000万円以上
- 再雇用で年収が増える
- 副業収入がある
- 企業型DC・iDeCoを複数運用している
- 個人年金・保険など受け取りが複数ある
- 家族の所得や扶養の関係が複雑
特に
「退職金+給与+副業+年金」 が重なると税金が跳ね上がることがあります。
ここが重要!
→ 複数収入がある人ほど「受け取り方一つ」で税金が激変します。
退職金の運用と税金|投資・不動産・金・仮想通貨の注意点

退職金を受け取った後、「どう運用すべきか?」は大きな悩みですよね。
実は、退職金の運用は 株式・投資信託・不動産・金(ゴールド)・仮想通貨 など選択肢が多い一方で、税金の仕組みが複雑になりやすいのが特徴です。
たとえば、投資信託や株はNISAやiDeCoを使えば売却益が非課税になる一方、通常口座での売却は20%の税金がかかります。
不動産投資は経費が使えますが、固定資産税や修繕費、空室リスクなども考慮が必要です。
さらに、金(インゴット)やビットコインなどの暗号資産は、売却益が雑所得扱いで税率が最大55%まで上がる可能性があり、海外取引や海外移住の際には追加リスクも発生します。
つまり、退職金運用では「どの資産で、どの口座で、いつ売買するか」で税金が大きく変わるということですね!
この章では、主要な投資ごとの税金の仕組みと注意点を、初心者にもわかりやすく徹底解説します。
9-1. 株・投資信託・NISA・iDeCoを使った投資税金対策と売却益の注意点
株式・投資信託の税金はシンプルですが、
NISA・iDeCoを使うと節税効果が一気に大きくなります。
📌 通常の課税
- 売却益に 20.315%
- 配当にも課税される
📌 NISAのメリット
- 売却益が 完全非課税
- 退職金の投資先として最も使いやすい
📌 iDeCoのメリット
- 運用益が非課税
- 掛金が所得控除
- 受け取り時に退職所得控除・公的年金控除が使える
📌 注意点
- NISAは枠が決まっている
- iDeCoは60歳まで引き出し不可
ここが重要!
→ 退職金の運用は「まずNISA、次にiDeCo」が最適ルートです。
9-2. 不動産投資・マンション購入・駐車場経営による不動産投資税金対策
不動産投資は節税効果が大きい一方、仕組みが複雑です。
しかし、うまく活用すれば「所得圧縮」に非常に有効です。
📌 節税できるポイント
- 建物部分の減価償却
- 物件の修繕費
- 住宅ローン金利
- 管理費・保険料
- 減価償却で赤字を作り所得税を抑える
📌 注意点
- 空室リスク
- 修繕費の発生
- ローン金利の上昇
- 相続時の土地評価が変動
不動産は節税効果が高い分、リスク管理は必須です。
9-3. 金購入・インゴット・ビットコインなど暗号資産税金対策と海外口座・海外移住のリスク
金・暗号資産は値動きが大きく、利益が出たときの税金も重くなりがちです。
特に仮想通貨は他の資産と税制がまったく違います。
📌 金(ゴールド)
- 売却益は 譲渡所得
- 保有期間5年超で税率優遇あり
- インゴットは売却時の本人確認義務がある
📌 ビットコイン・暗号資産
- 利益は 雑所得(最大55%課税)
- 給与・副業収入と合算
- 税金が跳ね上がるので注意
📌 海外口座・海外取引のリスク
- 海外移住しても税務申告が必要な場合あり
- 金融庁・国税庁の管理が強化
- 海外の税制との二重課税に注意
ここが重要!
→ 暗号資産は税率が非常に高いので、高額退職金との組み合わせには要注意です。
結論
退職金2,000万円・3,000万円をしっかり守るためには、退職前後の税金対策をどれだけ早く始められるかが勝負です。
退職所得控除・ふるさと納税・iDeCo・NISA・法人化・相続対策など、どれも仕組みを知っているかどうかで手取り額が100万〜300万円以上変わることも珍しくありません。
つまり、あなたが今すぐやるべきことは次の3つです。
①「退職金の税金の仕組み」を理解する
退職所得控除や受け取り方によって、税金は大きく変わります。
まずはここを知るだけで手取りが増えるケースが多いです。
② ふるさと納税・iDeCo・NISAなど“退職前にできる節税”を実行する
タイミングを間違えると控除が減るため、退職前の準備がとても重要です。
③ 専門家(税理士・FP)に相談して最適なプランに整える
退職金・副業・相続・法人化は専門知識が必要ですが、
専門家を使えばあなたに最も有利な方法をカスタマイズしてくれます。
退職金は一生に一度の大きなお金。
正しい知識と対策を実践すれば、老後資金を最大限に守り、資産を増やしながら安心して生活できます。
今日できることは「控除」「受け取り方」「節税策」を見直すことからです。
小さな一歩が、将来の大きな安心につながります。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!









コメント